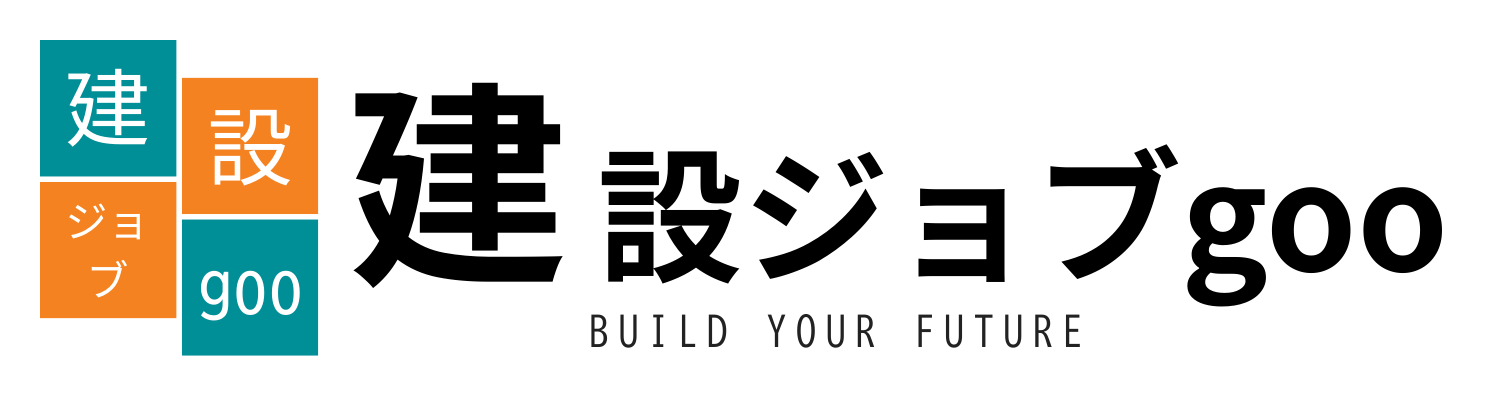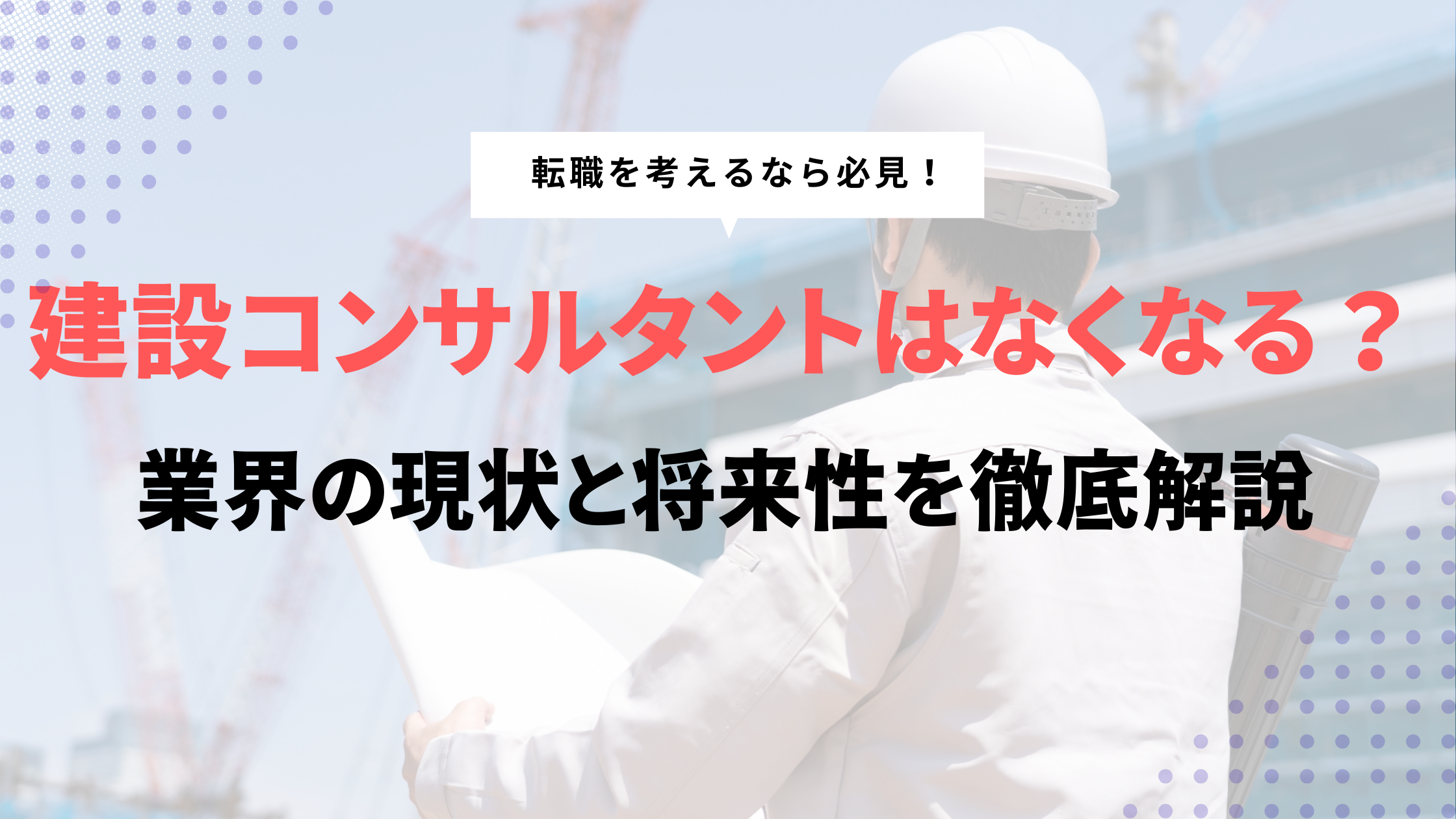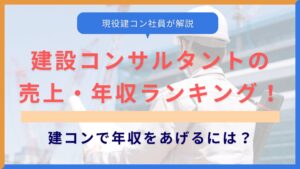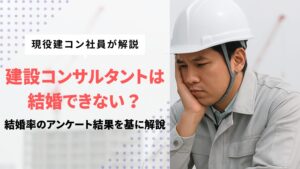「建設コンサルタントって、将来性がないって本当?」
「AIに仕事が奪われてなくなるって聞くけど、大丈夫?」
もしあなたが今、建設コンサルタントへの転職を考えているなら、あるいは現職でのキャリアに不安を感じているなら、そうした疑問を抱えているかもしれません。しかし、これらの言葉だけを鵜呑みにするのは危険です。
結論から言えば、建設コンサルタントの仕事がなくなることはありません。
本記事では、なぜ「建設コンサルタントがなくなる」と言われるのか、その理由を解説しつつ、それでも「なくならない」と言える根拠と、将来性について徹底的に掘り下げていきます。
 ぽむ
ぽむ建設コンサルタントは、社会インフラを支えるやりがいの大きな仕事である上、給与水準も高く人気のある職種!だから、興味のある人も多いんだけど、「なくなる」なんてことを聞くと不安になるよね。今日はその「誤解」を解いていこう!
\クリックで読みたいところに飛べるよ/
建設コンサルタントが「なくなる」と言われる理由
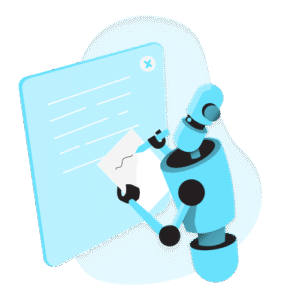
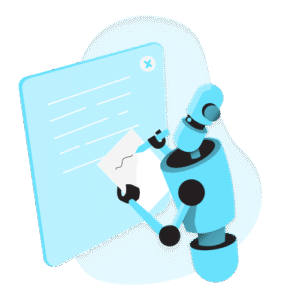
なぜ建設コンサルタントの仕事は「なくなる」とささやかれるのでしょうか。その背景には、主に以下の4つの大きな変化があります。
- 公共事業の縮小とその影響
- AI等による技術革新と業務の自動化
- 若手人材不足と高齢化
- 他業界との競争激化



一緒にひとつずつ見ていこう!
公共事業の縮小とその影響
まず、公共事業の予算規模が縮小傾向にあることが挙げられます。日本はかつて、高度経済成長期に集中的なインフラ整備を進めてきましたが、今後は新規の構造物建設は減っていくと見られています。
特に、国の公共事業を支えてきた「防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策」が令和7年度に終了します。これにより、大規模な新規の道路やダム、橋梁などの新設設計業務は減少していくでしょう。
加えて、日本全体での人口減少も影響しています。多くの地方都市では、将来を見据えた「コンパクトなまちづくり」が進んでおり、不要になった橋や道路などのインフラをダウンサイジング、あるいは撤去する動きも出てきています。
新規インフラの減少と、人口減少に伴うインフラの適正化は、新設構造物の設計を主とする建設コンサルタントにとって、業務量が減少する要因となり得ます。
AI等による技術革新と業務の自動化
AI等の技術の進歩が、建設コンサルタントの仕事を効率化し、ひいては仕事そのものを奪うのではないかという懸念もあります。
代表的なものが、BIM/CIM(Building/Construction Information Modeling, Management)やドローンの活用です。
- BIM/CIM:3Dモデル上で設計や施工情報を一元管理することで、設計のミスを減らしたり、関係者間の情報共有をスムーズにしたりできます。
- ドローン:地形測量や点検に活用することで、これまで膨大な時間と人手がかかっていた作業を、短時間で効率的に行えるようになりました。
これらの技術は、従来の設計や調査業務のあり方を大きく変えつつあります。これまで何人もの技術者が数週間かけて行っていた作業が、最新技術によって短期間で完了するようになれば、業務量そのものが減ってしまうと考える人も少なくありません。
若手人材不足と高齢化
建設コンサルタント業界は、慢性的な若手人材不足と高齢化という構造的な問題を抱えています。
日本の生産年齢人口が減少する中で、建設業界全体の担い手不足は深刻です。「建設コンサルタンツ企業年金基金」によれば、建設コンサルタントにおける年齢構成は50代前半が最も多く、高齢化が進んでいます。
このままでは、ベテラン技術者が引退した際に、知識や技術が次世代に引き継がれず、業界全体の技術力が低下してしまうリスクがあります。AIやITツールへの依存度も高まり、技術伝承が進まないという悪循環に陥る可能性も。
他業界との競争激化
建設コンサルタントは、他の業界との競争にもさらされています。
IT・コンサルティング業界は、高い給与水準や柔軟な働き方を提示することで、優秀な若手人材を惹きつけています。建設コンサルタント業界は、こうした業界と比較される中で、「給料が低い」「働き方が古い」といったイメージを持たれがちです。
賃金や働き方における魅力で劣ってしまうと、優秀な人材が他業界に流出し、建設コンサルタント業界全体の活力が失われてしまうのではないかという懸念も、無視できない問題です。



最近では、新3K(給与・休暇・希望)の取り組みで、少しずつだけど労働環境は改善傾向にあるよ!
建設コンサルタントが「なくならない」と言える理由
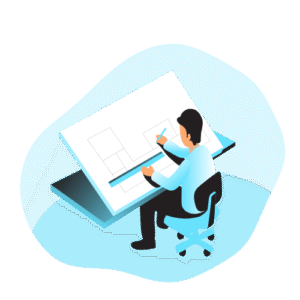
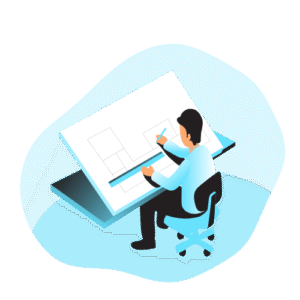
公共事業の縮小や技術革新によって「なくなる」とささやかれる建設コンサルタントですが、その一方で、将来にわたって必要不可欠な存在であり続ける確固たる理由が明確に存在します。



数年前と比べると働き方が変わっていることは事実だけど、実際に働いている僕の見解としては、「なくなる」ということはまずないと言えるよ(少なくとも後数十年は)!
その理由を順番に見ていこう!
社会インフラの維持管理・更新需要
日本の社会インフラは、高度経済成長期に集中的に整備されました。これらの多くが建設から50年以上が経過し、一斉に「維持管理・更新」の時期を迎えています。
例えば、全国に約73万橋ある橋梁のうち、建設後50年を経過する橋の割合は、2023年時点では約25%ですが、2033年には約53%にまで急増すると見られています。老朽化した橋梁や道路、トンネルを安全に使い続けるためには、国の定めにより、重要構造物は5年に一度の定期点検が義務付けられています。この点検で見つかった損傷や劣化の程度を正確に診断し、最適な補修方法を検討・設計することは、高度な専門知識と経験を要する業務であり、今後も必要とされ続ける仕事であると言えます。
高度な専門知識の必要性
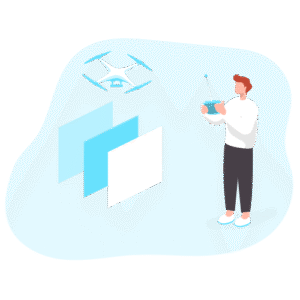
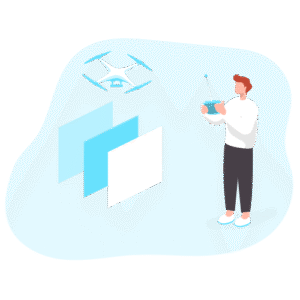
BIM/CIMやドローンといった技術は、確かに建設コンサルタントの業務を大きく効率化しました。しかし、これらの技術はあくまでも「技術者の補助ツール」に過ぎません。
例えば、BIM/CIMは、関係者への説明を視覚的に補助したり、各プロセス間の連携をスムーズにするためのツールであり、最終的な設計判断を下すのは技術者です。また、ドローンも、地形測量や航空写真・点群データを取得し、設計材料を手に入れる役割を担いますが、その膨大なデータをどのように解析し、どのような設計に落とし込むかという判断は、専門知識を持つ技術者でなければ不可能です。
さらに、AIによる画像解析技術で橋梁の損傷を診断する研究も進んでいますが、まだまだ発展途上です。ひび割れの幅や深さ、コンクリートの劣化具合などを総合的に判断し、最適な補修方法を提案するには、長年の経験と高度な専門知識が必要不可欠です。現時点では、AIの診断結果は参考情報であり、それ単体で成果品として使用するには性能が低すぎると言わざるを得ません。
公共事業の不可欠性
公共事業は、国の経済活動や国民生活を支える上で欠かせないものです。災害時の迅速な復旧や、国土強靭化計画の推進において、建設コンサルタントは中心的な役割を担います。
2024年の能登半島地震の際も、道路啓開や液状化対策、地盤の復旧など、多岐にわたる分野で建設コンサルタントが災害復旧の最前線で活躍しました。このような緊急事態において、即座に専門的な知見と技術を提供できる存在は、他にありません。
防災・減災分野での役割拡大も見逃せません。近年、ひっ迫する巨大地震や、激甚化・頻発化する豪雨などの自然災害への備えは、喫緊の課題です。堤防や砂防堰堤などのハード対策に加えて、ハザードマップの作成や被災地の迅速な復旧・復興計画の策定などのソフト対策の需要も高まっています。
「なくならない」と言える最大の理由は、建設コンサルタントが、公共の安全と安心を守る、なくてはならない存在であることなのです。
官民連携や新分野進出
これまでの新設需要が減少する一方で、公共事業に民間の活力を導入するPPP/PFI事業や、地域課題の解決を支援する業務など、これまでとは違った新たな分野での需要が拡大しています。
また、脱炭素社会の実現に向けて、再生可能エネルギー(風力、太陽光、地熱など)や環境分野での活躍の場も広がっています。建設コンサルタントは、これまでのインフラ整備で培った技術的な知見と、プロジェクトを推進するマネジメント能力を活かし、活躍の場を広げています。
技術者単価は13年連続上昇
国土交通省が公表しているデータ(令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価について)によると、建設コンサルタントの技術者単価は、平成24年度から13年連続で上昇を続けています。
世間一般の給与が停滞する中、これは国が土木技術者の専門性を高く評価し、その労働環境を改善しようと努めている証拠と言えるでしょう。このデータは、「土木技術者が社会から必要とされている証拠」として、建設コンサルタントの将来性を裏付ける大きな説得力を持っています。
建設コンサルタントの将来性とキャリア展望
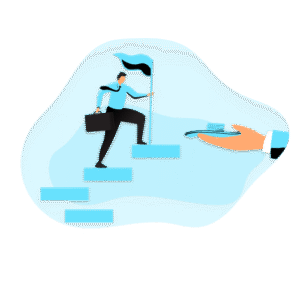
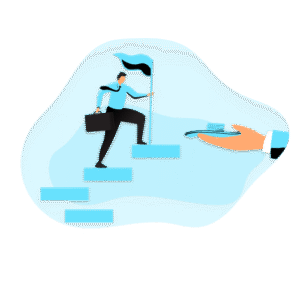
建設コンサルタントの仕事は、今後も社会に必要とされ続けます。では、この業界でキャリアを築いていくには、どのような将来性があるのでしょうか。



変わりつつある建設コンサルタントの働き方。具体に将来はどのようになっていくのかを見ていこう!
「なくなる」と言われる建設コンサルタントの将来性はとキャリア展望
インフラ整備の長期的需要
人口減少下でも、社会基盤の整備は止まりません。特に、地方の活性化や、都市部の再開発には、建設コンサルタントの知見が不可欠です。また、AIやIoTなどの最新技術をインフラ管理に取り入れる「インフラDX」への対応も、今後の重要なテーマとなります。デジタル技術を駆使してインフラの状況をリアルタイムでモニタリングし、効率的な維持管理計画を策定する能力は、これからますます価値を高めていくでしょう。
技術革新と人材育成の重要性
AIやDXは、仕事を奪うのではなく、むしろ業務を効率化し、より創造的な仕事に集中できる環境を整えてくれます。今後は、「技術力」に加え、AIやDXを使いこなす「マネジメント能力」を併せ持った「ハイブリッド人材」が求められるようになります。
例えば、AIが膨大なデータを分析して最適な設計案を複数提示する時代になれば、技術者はその中から最適なものを選び、クライアントに説明し、合意を形成する能力がより重要になります。これからの時代に生き残るのは、技術革新を恐れず、積極的に学び、新しいツールを使いこなせる人材です。
国際展開と海外需要
新興国では、これから本格的なインフラ整備が進められます。日本のインフラ技術、特に高度な専門性が求められる橋梁やトンネルの設計技術は世界から高い評価を得ています。国際協力機構(JICA)や国際コンサルティング案件への参加機会も広がっており、海外でのキャリアを視野に入れることも可能です。
長く働ける求人・転職の探し方
将来を見据えた転職活動では、以下のポイントを意識することが重要です。
- AI・DXに積極的な企業:技術革新に乗り遅れる企業は、今後生き残ることが難しいでしょう。DX投資に積極的で、社員のスキルアップを支援している企業は、将来性があると言えます。
- ワークライフバランスを重視する企業:昭和・平成初期の「仕事が第一」という価値観から、家庭などのプライベートを重要視する流れが主流になっています。ワークライフバランスの取れない企業は、優秀な人材が集まらず、結果として成長が停滞してしまう可能性があります。なお、建設コンサルタントのホワイト企業の見分け方やブラック企業の回避方法については、「建設コンサルタントのホワイトランキング|失敗しない【見分け方】」で解説しておりますので併せてご覧ください。
- 専門資格(土木技術士・RCCMなど)のキャリア価値:土木技術士やRCCMといった専門資格は、あなたの市場価値を高め、転職活動を有利に進める上で大きな武器となります。中には、最年少で技術士を取得し、その資格を武器に転職したことで人生が変わったという人もいるほどです(筆者もその一人です)。専門性を証明する資格は、あなたのキャリアを大きく後押ししてくれるでしょう。


【総括】建設コンサルタントはなくなる?業界の現状と将来性を徹底解説
「建設コンサルタントはなくなる」と言われる背景には、公共事業の縮小、技術の自動化、そして人材不足といった、業界が抱える課題があることは事実です。
その一方で、老朽化した社会インフラの維持管理や、頻発する自然災害への備えといった、建設コンサルタントでなければ担えない重要な社会的役割は、今後ますます増大していく可能性もあります。
これからの時代に生き残るのは、単に技術力があるだけでなく、技術革新を恐れず、AIやDXを使いこなし、専門性と柔軟な働き方を両立できる「ハイブリッド人材」です。
自分の強みを活かしつつ、今後も求められるスキルを身につけていけば、建設コンサルタントとして長く活躍し続けることができるでしょう。