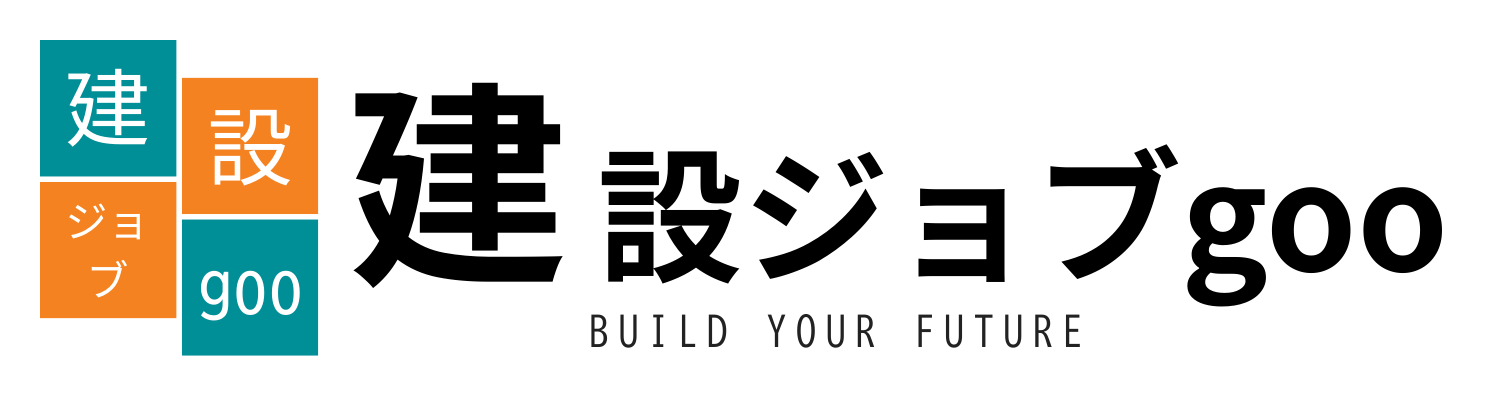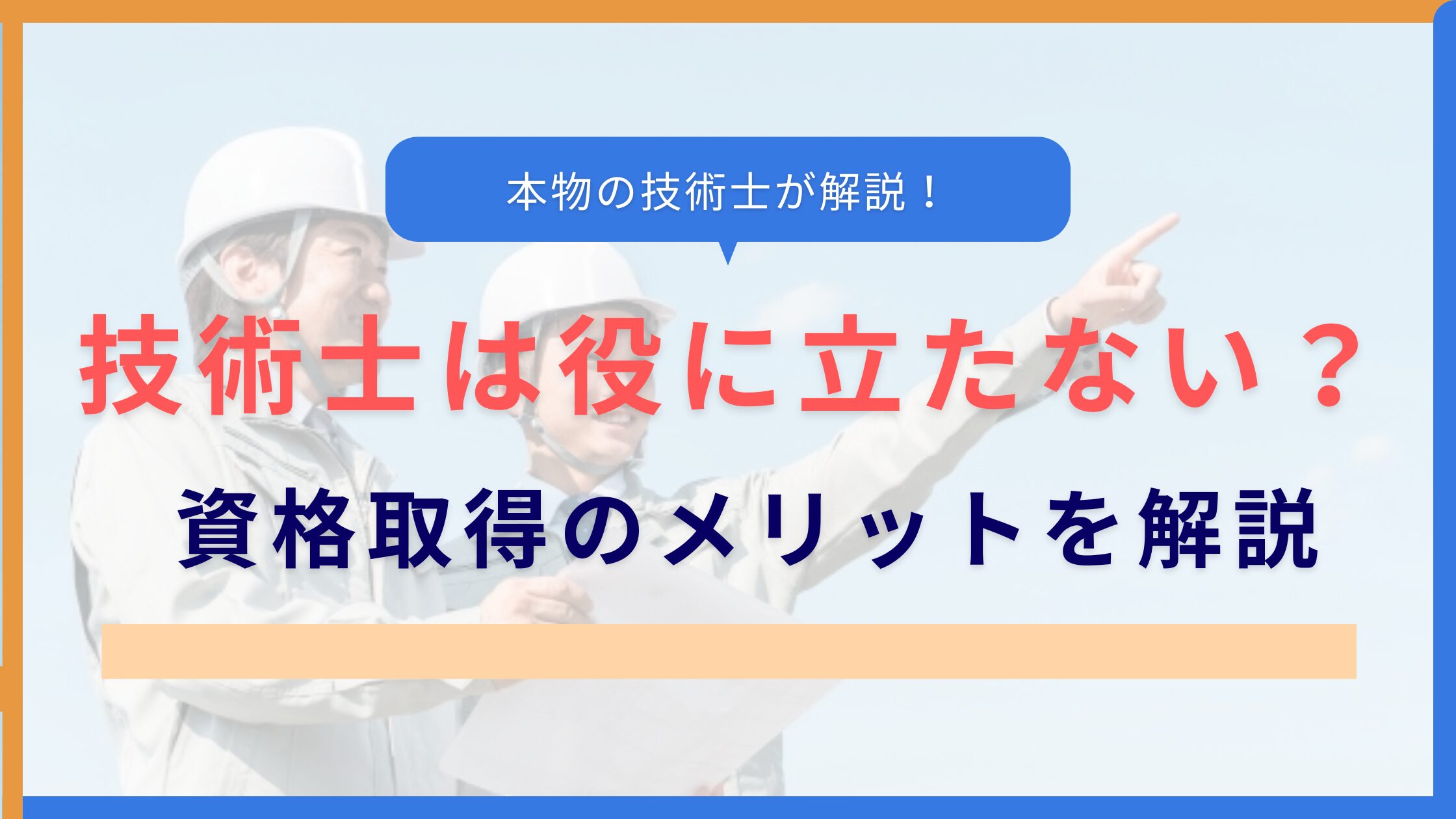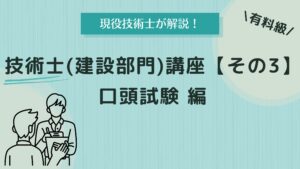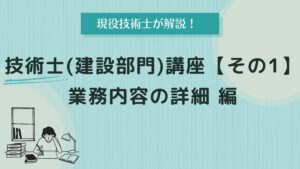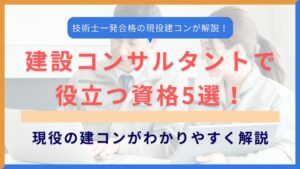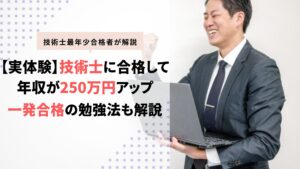新人くん
新人くんぽむさん!僕技術士の取得に向けて勉強してるんですけど、「技術士は役に立たない」っていう噂を聞いて不安になって…。



確かにそういわれることもあるよね。でも技術士は確実に役立つ資格だよ!その理由を解説していくね!
\クリックで読みたいところに飛べるよ/
※この記事は、主に技術士 建設部門について解説しております。
技術士試験の概要や取得方法についてはこちらの記事で解説しております。
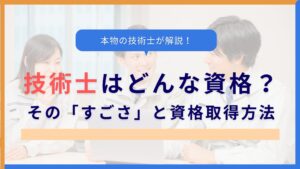
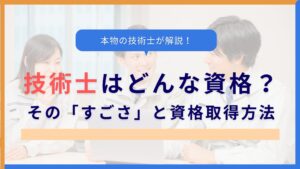
技術士が役に立たないと言われる理由


技術士が役に立たないと言われる理由は主に以下の5つです。
- 理由① 業務独占資格ではない(資格なしでも仕事はできる)
- 理由② RCCMでも代用できる
- 理由③ 試験内容と日常業務のギャップがある
- 理由④ 費用・時間対効果
- 理由⑤ 知名度・使い方の曖昧さ
理由① 業務独占資格ではない(資格なしでも仕事はできる)
技術士は、医師や弁護士のような「資格がなければできない」という業務独占資格ではありません。
たとえば、建設コンサルタントや設計業務、調査業務などは、技術士資格がなくても従事することは可能です。
そのため、現場の第一線では「資格がなくても同じ仕事をしている人がいる」という現象が起こり、役に立たないように見えるのです。
理由② RCCMでも代用できる
建設コンサルタント業界では、RCCM(シビルコンサルティングマネージャ)の資格も高い評価を受けています。
RCCMは、国交省の登録要件や入札評価で活用できることが多く、これができるのは主に技術士とRCCMだけです。
それにもかかわらず、RCCMは技術士に比べて資格取得のハードルが格段に低いことから、RCCMを取得して技術士の代わりとして用いるケースが多く見られます。
それでもやはり、技術士の方が入札時には高く評価されるため、国交省や都道府県の大きな案件となるとRCCMでは難しいところもありますが、小さな市町村を主の顧客とする建コンではRCCMでも十分に戦っていけるでしょう。これも役に立たないと言われる理由の一つです。
理由③ 試験内容と日常業務のギャップがある
技術士試験は、専門的な知識に加え、倫理観・社会的課題・マネジメント力などの総合力を問われます。
しかし実際の現場業務は、限られた範囲の技術や経験を求められることが多く、試験内容が実務と直結しにくいのが現状です。
そのため、勉強に時間を費やしても実務スキルが向上しないため、役に立たないと感じる人が少なくありません。
一方で、試験勉強を通じて体系的に知識を整理し、課題解決能力を高められる点は大きなメリットです。
目先の実務ではなく、将来のマネジメント職やコンサルティング職を見据える人には大きな価値となります。
理由④ 費用・時間対効果
技術士試験は、合格率10〜15%前後と難関です。
1〜2年単位での勉強が必要になることも多く、仕事と両立するにはかなりの努力と時間が求められます。
さらに、受験料・講座費用などのコストもかかります。合格後も、登録費・年会費・継続研さん(CPD)などが必要です。
そのため、「これだけの投資に対して、リターン(昇給・昇進・転職優位性)が見合わない」と感じる人も少なくありません。
一方で、会社によっては資格手当や昇進条件として明記しているところもあり、「自分の職場ではどれくらい評価されるのか」を事前に確認することが重要です。
理由⑤ 知名度が低い
技術士は建コンや建設業界では権威ある資格ですが、一般社会での認知度は高くありません。
「技術士」と名乗っても、非技術系の人には価値が伝わりにくく、建コン等の市場以外では評価されにくいのが現状です。
例えば、行政書士や宅建士、FPなどの資格は需要も大きく様々な分野で評価されるため、ぼんやりとしたキャリアプランで取得しても後からうまく使いこなすことは可能です。
しかし、技術士の場合は、活かせる業界が限られるため、「これから建コン・建設業界に長く従事したい」という思いがなければ、取得しても役に立たない資格となってしまいます。
技術士のすごさ・メリットはあるの?
ここまでは、「技術士が役に立たないと言われる理由」というネガティブ要素について説明してきました。
しかし、技術士は役に立たないどころか建コン業界、建設業界では最重要資格です。
ここからは、技術士のすごさとメリットについて解説していきます。
なお、詳細については、こちらの記事で解説しておりますので、本記事では概要を解説いたします。
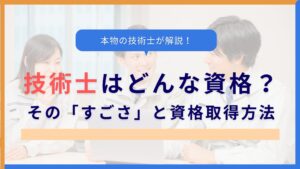
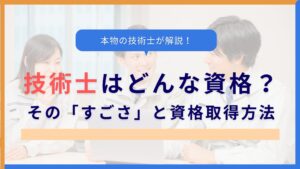
技術士のすごさは何?


① 国家資格の中でも最高位の位置づけ
「技術士法」という法律に基づいた、技術分野の最高峰の国家資格です。弁護士や公認会計士と並ぶ5大国家資格とされており、専門職の国家資格として、その社会的地位は非常に高く評価されています。
② 合格率10%前後の超難関
技術士試験の最大の特徴は、非常に低い合格率です。特に第二次試験は合格率が例年10%前後と非常に低く、狭き門として知られています。この難易度の高さが、技術士の希少性と価値を高めています。
- 一次試験:合格率 約30〜50%
- 二次試験:合格率 約10%
③ 実務経験が必須
技術士になるためには、一定の実務経験年数が必要です。
たとえば大学卒業後に受験する場合でも、最低でも7年以上の実務経験を要します。
④ 社会的信頼とブランド(官公庁・企業で評価)
技術士資格は、官公庁や自治体、建設コンサルタント業界で高く評価されています。
- 公共事業の入札加点
- 建設コンサルタントの登録要件
- 企業の昇進・資格手当制度
⑤ 海外でも認知される専門資格
技術士資格は、国際的な技術者資格である「APEC Engineer」や「International Professional Engineer」に登録するための要件を満たしています。
技術士を取得するメリットは?


① 公共事業の入札や技術提案に参加できる
建設コンサルタント業界などでは、技術士の資格保有者が在籍していなければ入札に参加できない案件が数多くあります。
特に国や自治体が発注する公共事業では、技術士が管理技術者として業務を管理することが求められるケースもあります。
② 高度な専門性の証明になる
「技術士」という肩書きは、社会的な信頼を大きく高めます。
たとえば、同じ説明をしても、「技術士が言うなら信頼できる」という評価を得られるケースも多くあります。
③ 年収アップ・キャリアアップにつながる
多くの企業では、技術士資格を持っていることで資格手当や昇格の優遇が受けられます。
また、建設コンサルタントやゼネコンでは、部長や所長の資格要件として指定されていることもあり、より責任あるポジションに抜擢されるチャンスが増えます。
技術士の年収事情についてはこちらの記事で詳しく解説しております。
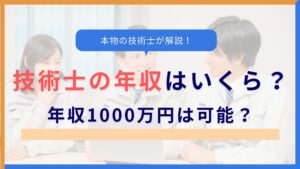
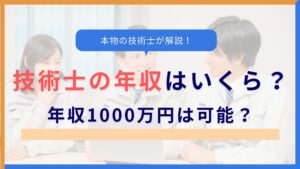
④ 転職・独立に強くなる
技術士は、転職市場でも非常に強い資格です。
特に建設コンサルタント業界では、即戦力人材の証明として高く評価されます。
さらに、独立してコンサルタントとして開業することも可能です。
建設コンサルタント業界の転職の流れについて知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。
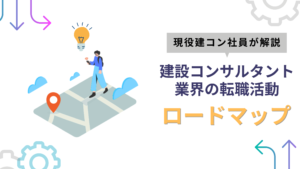
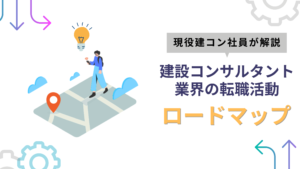
技術士はどんな人が目指すべき?


技術士(建設部門)は主に建設コンサルタントや建設関連の業界で活用できます。特に、建設コンサルタント業界では「いつかは技術士」と志す人が多く、「看護師で言う看護師資格」、「弁護士で言う弁護士資格」のような存在です。
このため、建設コンサルタントを目指す方にとっては必ず視野に入れたい資格となります。
建設コンサルタント業界について詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にして下さい。


特に、以下のような思いのある方には技術士の取得をお勧めします。
- 専門性を身に着けて評価されたい
- コンスタントに出世したい
- 業務の管理技術者として従事したい(特に国交省業務)
- 将来的に同業界で転職・独立したい
これらは、類似資格のRCCMでは難しいことが多く、技術士の取得をお勧めします。
【総括】技術士は役に立たない?資格取得のメリットを本物の技術士が解説!
「技術士は役に立たない」と言われるのは、“資格を取る目的”が曖昧なまま勉強を始めてしまう人が多いからです。
確かに、業務独占資格ではなく、費用や時間もかかるため、短期的なメリットは見えにくいでしょう。
しかし、公共事業・マネジメント・独立・キャリアアップなど、明確な目的を持つ人にとっては、技術士資格は「強力な武器」になります。
最も重要なのは、「なぜ取りたいのか」「どう活かすのか」を明確にすること。
資格はゴールではなく、あなたの専門性を社会で発揮するための“スタートライン”です。
今後も本サイトではあなたの技術士取得を徹底的にサポートしますので、一緒に頑張っていきましょう!