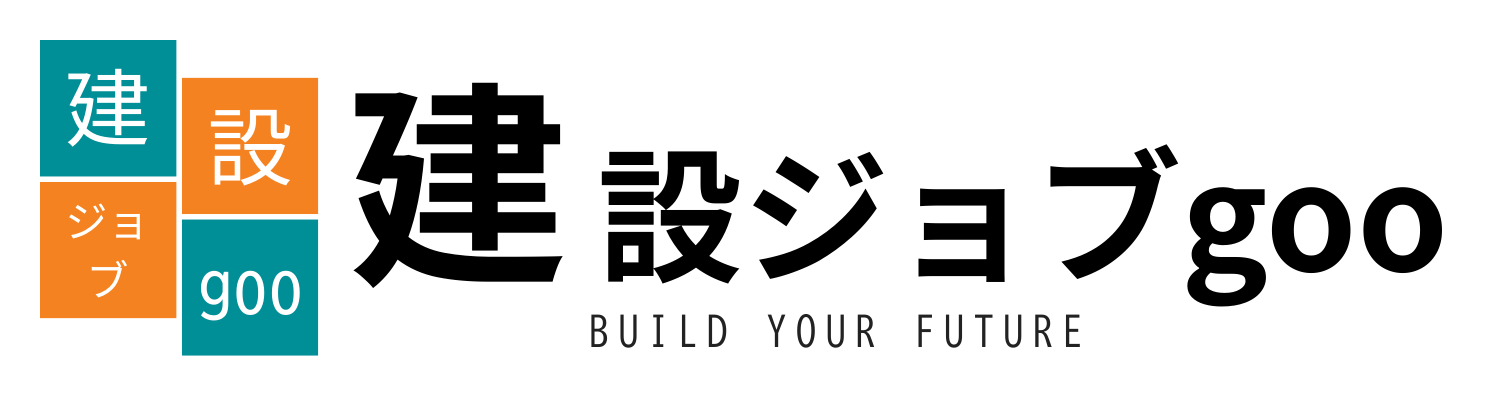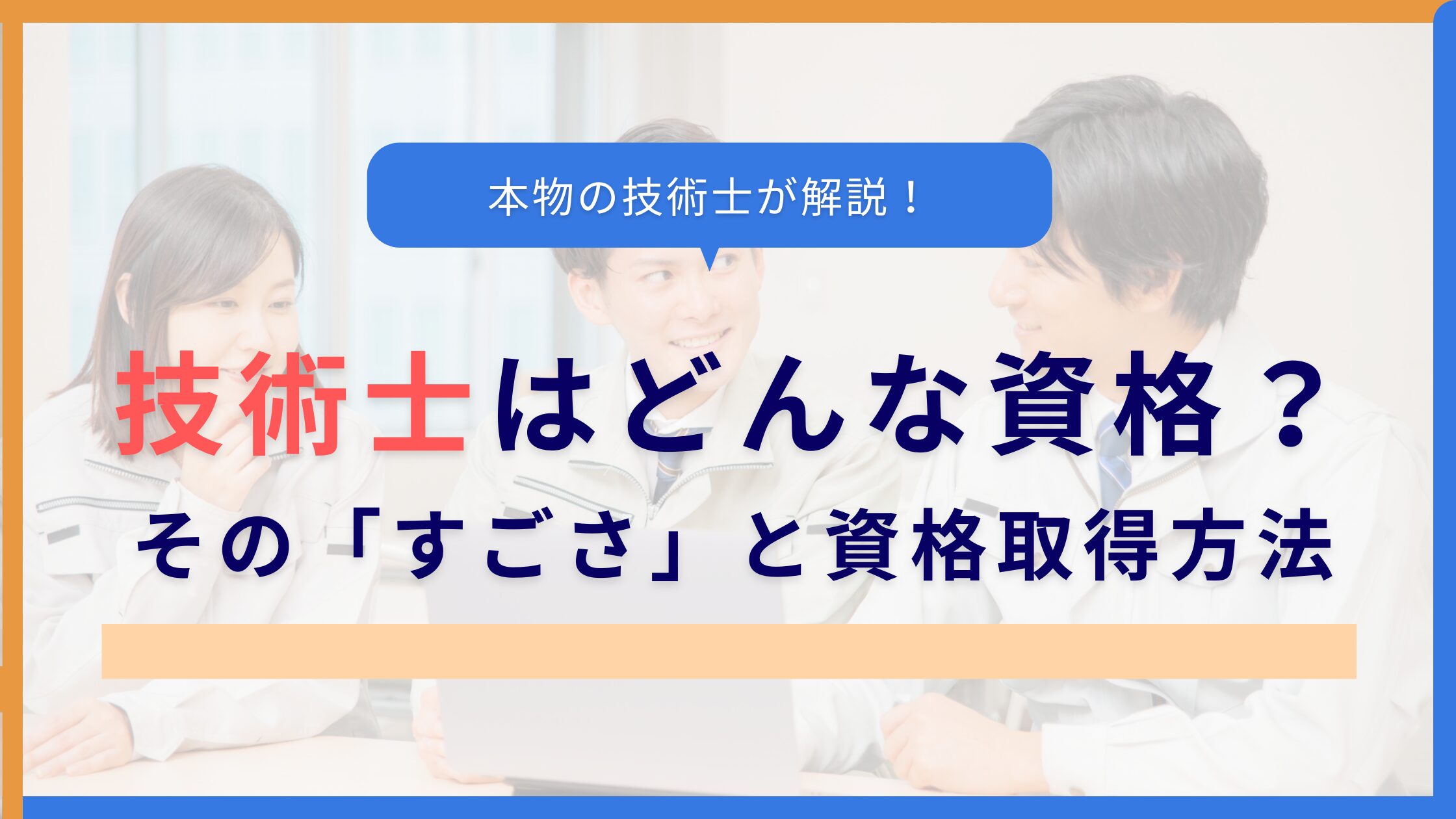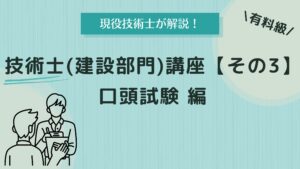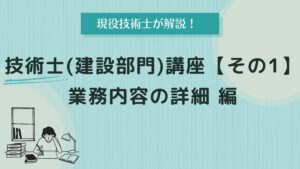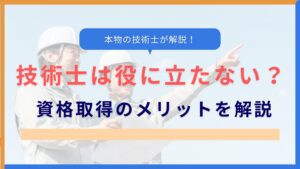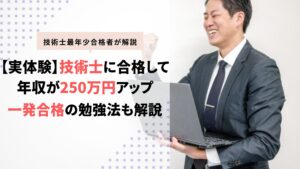新人くん
新人くんぽむさん!建設コンサルタントや建設業界では技術士資格が重要って聞きました!技術士ってどんな資格で何ができるのですか?



そのとおり!建コンでは技術士にしかできないことがあり、非常に重要なんだ!今回は技術士について、その「すごさ」や資格取得の方法を解説していくよ!
\クリックで読みたいところに飛べるよ/
※この記事では技術士の建設部門を中心に解説しております。
技術士はどんな資格?


まず、「技術士」という言葉を聞いたことはあっても、具体的にどんな資格なのか、どんな立場の人が持っているのかを正確に理解している人は少ないかもしれません。
ここでは、国家資格としての位置づけや、関連資格との違い、そしてその多様な分野について整理します。
技術士はどんな資格?
技術士とは、公益社団法人日本技術士会が運営する国家資格です。
技術士法に基づく資格であり、技術系資格の最高峰とも呼ばれています。
この資格の大きな特徴は、単なる知識試験ではなく、実務能力を証明する資格であるという点です。
試験では、理論だけでなく「技術的課題をどう解決するか」「社会的影響を踏まえてどう判断するか」といった実務応用力や倫理観が問われます。
つまり、机上の知識だけでなく、現場経験に裏打ちされた「真の技術力」を持つ人材でなければ合格できません。
また、技術士は「技術士法第二条」によって以下のように定義されています。
科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)を行う者
引用:公益社団法人 日本技術士会「技術士関係法令集」
難しい言葉が並んでいますが、要は、技術の責任者・指導者として社会に貢献する存在なのです。
技術士補との違いは?
技術士試験は一次試験と二次試験の2段階に分かれています。
一次試験に合格すると「技術士補」として登録が可能になります。
これは、技術士の補助的立場として位置づけられる資格で、まだ「技術士」としての独立した業務は行えません。
実務経験を積み、二次試験に合格して初めて「技術士」として名乗ることができます。
| 区分 | 試験内容 | 合格後の資格 | 位置づけ |
|---|---|---|---|
| 一次試験 | 基礎・適性・専門の筆記 | 技術士補 | 技術士を目指すための登竜門 |
| 二次試験 | 専門分野の記述・論文・口頭試験 | 技術士 | 実務と責任を担う専門職 |
つまり、技術士補は“候補者”であり、技術士は“プロフェッショナル”。
資格の重みが大きく異なります。
なお、JABEE認定プログラム修了者は、技術士の第一次試験が免除され、大学卒業後、申請により技術士補に登録が可能です。
技術士資格に関する一覧表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 認定団体 | 日本技術士会 |
| 受験制度の流れ | – 第一次試験 → 合格者は技術士補登録(または指定教育課程修了者は技術士補) → 実務経験を経て第二次試験 → 合格後、技術士登録 |
| 第一次試験 受験資格 | 学歴・年齢などの制限なし。誰でも受けられる。 ただし、JABEE 認定教育課程を修了した者は第一次試験を免除され技術士補と見做される制度がある。 |
| 第二次試験 受験資格 | 第一次試験合格後、かつ一定の実務経験を満たすこと。具体的には以下いずれか: ① 技術士補登録後、技術士の指導下で4年以上実務経験 ② 技術士補取得後、監督者の下で4年以上実務経験 ③ 実務経験7年以上(第一次合格前後を合算可) (いずれかを満たせば第二次試験出願可) また、平成15年度以降、第二次試験受験者は第一次試験合格者または指定教育課程を修了した者が対象となる。 |
| 試験スケジュール(公示例) | – 受験申込書配布開始:3月下旬ごろ – 申込み受付:4月 – 筆記試験:7月中旬頃 – 筆記合格者対象の口頭試験:年末〜翌年初頭 – 合格発表:最終(口頭含む)は3月中旬ごろ |
| 試験方式 | – 筆記試験(必須科目+選択科目) – 口頭試験(筆記合格者を対象) – 論述・記述試験を重視 – 試験区分は、総合技術監理部門と各専門部門等がある |
| 試験科目・構成 | – 必須科目:技術者の共通知識・応用能力を問う設問 – 選択科目:受験者が選んだ技術部門に関する専門性(例:鋼構造、都市計画、建設環境等) – 論文・記述形式の出題が中心 – さらに口頭試験で技術的説明・質疑応答を行う |
| 受験料・登録料等 | – 一次試験受験手数料:13,000 円 – 二次試験受験手数料:20,500 円 – 登録手数料:8,100 円 ※2026年から値上げ(上記は値上げ後の価格) |
| 合格基準・基準例 | 各科目での基準点を満たすこと、総合得点基準もクリアすること 詳細な配点や基準は年度・部門ごとに公表される(日本技術士会案内に準拠) |
技術士21部門の概要
技術士の専門分野は多岐にわたり、社会のあらゆる技術領域をカバーしています。
全21の部門にわかれており、それぞれの部門別に試験が実施されます。
技術士21部門一覧表
| No. | 部門名 | 主な業務分野 |
|---|---|---|
| 1 | 機械 | 機械設計、生産システムなど |
| 2 | 船舶・海洋 | 船舶の設計、海洋開発など |
| 3 | 航空・宇宙 | 航空機・宇宙機の開発、ロケット工学など |
| 4 | 電気電子 | 電気設備、電子回路、半導体など |
| 5 | 化学 | 化学プラント、素材開発、環境化学など |
| 6 | 繊維 | 繊維製品の製造技術、新素材開発など |
| 7 | 金属 | 鉄鋼、非鉄金属、合金開発など |
| 8 | 資源工学 | 鉱物資源、石油、天然ガス開発など |
| 9 | 建設 | 道路、橋、ダム、トンネル、都市計画など |
| 10 | 上下水道 | 上水道・下水道施設の計画、設計、維持管理 |
| 11 | 衛生工学 | 廃棄物処理、環境衛生、公害防止など |
| 12 | 農業 | 農業土木、農芸化学、農業経済など |
| 13 | 森林 | 森林計画、林業技術、森林資源の管理など |
| 14 | 水産 | 漁業、水産加工、海洋環境保全など |
| 15 | 経営工学 | 生産管理、品質管理、ロジスティクスなど |
| 16 | 情報工学 | ソフトウェア開発、ネットワーク、情報セキュリティなど |
| 17 | 応用理学 | 物理、化学、地質、地球物理など |
| 18 | 生物工学 | 遺伝子工学、バイオテクノロジーなど |
| 19 | 環境 | 環境アセスメント、環境マネジメントなど |
| 20 | 原子力・放射線 | 原子力発電、放射線利用、安全管理など |
| 21 | 総合技術監理 | 技術プロジェクト全体のマネジメント |
このうち、建設部門の受験者数が圧倒的に多く、令和6年のデータでは21部門全体の受験者数が29,846人に対し、建設部門が17,730人と約6割の受験者が建設部門となっています。
また、各21部門の中でさらに細分化されており、「選択科目」というものが存在します。
ここでは一例として「建設部門」の選択科目を示します。
技術士 建設部門 選択科目一覧表
| No. | 選択科目(専門分野) | 主な業務内容の例 |
| 9-1 | 土質及び基礎 | 土質調査、地盤改良、基礎構造物、山留め工の計画・設計・施工 |
| 9-2 | 鋼構造及びコンクリート | 鋼構造物、コンクリート構造物の計画・設計・施工・維持管理、建設材料 |
| 9-3 | 都市及び地方計画 | 国土計画、都市計画、地域計画、土地利用、都市交通施設、市街地整備 |
| 9-4 | 河川、砂防及び海岸・海洋 | 治水・利水計画、河川構造物、砂防、地すべり防止、海岸保全、海洋構造物 |
| 9-5 | 港湾及び空港 | 港湾計画、港湾施設・構造物の設計・施工・維持管理、空港計画・施設 |
| 9-6 | 電力土木 | 電源開発計画、発電施設、取水・放水路構造物など、電力に関する土木構造物 |
| 9-7 | 道路 | 道路計画、道路施設・構造物の調査、設計、施工、維持管理・更新 |
| 9-8 | 鉄道 | 新幹線、普通鉄道、特殊鉄道など、鉄道の計画・施設・構造物 |
| 9-9 | トンネル | トンネル、地中構造物の計画、調査、設計、施工、維持管理・更新 |
| 9-10 | 施工計画、施工設備及び積算 | 施工計画、施工管理、維持管理・更新、施工設備・機械、建設ICT、積算 |
| 9-11 | 建設環境 | 建設事業における自然環境・生活環境の保全・創出、環境影響評価(アセスメント) |



こんなにたくさんの部門・科目があるんですね!



それだけ各分野に特化していて専門性が高いってことだよ!
技術士の「すごさ」5選!


技術士が「すごい」と言われる理由は、単なる資格の難易度や知名度にとどまりません。
ここでは、国家資格としての地位・試験制度・社会的評価など、多角的な観点から「すごさ」を解説します。
- ① 国家資格の中でも最高位の位置づけ(5大国家資格の1つ!)
- ② 合格率10%前後の超難関(一次・二次)
- ③ 実務経験が必須(即戦力証明)
- ④ 社会的信頼とブランド(官公庁・企業で評価)
- ⑤ 海外でも認知される専門資格(国際的評価)
① 国家資格の中でも最高位の位置づけ(5大国家資格の1つ!)
「技術士法」という法律に基づいた、技術分野の最高峰の国家資格です。弁護士や公認会計士と並ぶ5大国家資格とされており、専門職の国家資格として、その社会的地位は非常に高く評価されています。
つまり、技術士は国家に認められた技術の最高権威者であり、
「この人の技術判断は社会的に信頼できる」という国からのお墨付きがあるのです。
② 合格率10%前後の超難関(一次・二次)
技術士試験の最大の特徴は、非常に低い合格率です。特に第二次試験は合格率が例年10%前後と非常に低く、狭き門として知られています。この難易度の高さが、技術士の希少性と価値を高めています。
- 一次試験:合格率 約30〜50%
- 二次試験:合格率 約10%
また、合格には単なる知識だけでなく、論文作成能力や口頭試問での論理的な説明能力が求められます。
特に二次試験は、記述試験と口頭試験を通じて「専門知識・課題解決力・倫理観・表現力」が総合的に評価されます。
そのため、単なる暗記では太刀打ちできないのが現実です。
この難関を突破できるのは、限られた経験豊富な技術者のみ。
合格者が少ないからこそ、社会的な価値が高いのです。
③ 実務経験が必須(即戦力証明)
技術士になるためには、一定の実務経験年数が必要です。
たとえば大学卒業後に受験する場合でも、最低でも7年以上の実務経験を要します。
つまり、技術士は「経験を積んだ現場の実力者」であり、即戦力を超えた“指導的技術者”。
実際の試験の内容も「過去の経験を踏まえてどう解決するか」を問うため、実務力がないと合格できません。
この仕組みにより、技術士は単なる知識型資格ではなく、「経験」と「知識」を融合した総合的エンジニア資格」として認められています。
④ 社会的信頼とブランド(官公庁・企業で評価)
後ほど詳しく解説しますが、技術士資格は、官公庁や自治体、建設コンサルタント業界で高く評価されています。
たとえば:
- 公共事業の入札加点
- 建設コンサルタントの登録要件
- 企業の昇進・資格手当制度
など、技術士を保有しているだけで待遇や立場が大きく変わるケースが多いです。
また、履歴書や名刺に「技術士(建設部門)」と記載することで、一目で専門家としての信頼を得られます。
⑤ 海外でも認知される専門資格(国際的評価)
技術士資格は、国際的な技術者資格である「APEC Engineer」や「International Professional Engineer」に登録するための要件を満たしています。これにより、海外でも通用する国際的なプロフェッショナルとして活動できる道が開かれます。
技術士を取得するメリットは?何ができるの?


技術士の最大の魅力は、資格を持つことでキャリア・収入・信頼性のすべてにおいて大きな向上が見込める点です。
単なる「肩書き」ではなく、技術者としての実力と価値を証明する資格だからこそ、得られるメリットは多岐にわたります。
ここでは、特に代表的な5つのメリットを紹介します。
技術士を取得するメリット
- 公共事業の入札や技術提案に参加できる
- 高度な専門性の証明になる
- 年収アップ・キャリアアップにつながる
- 転職・独立に強くなる



ひとつずつ詳しく解説するよ!
① 公共事業の入札や技術提案に参加できる
建設コンサルタント業界などでは、技術士の資格保有者が在籍していなければ入札に参加できない案件が数多くあります。
特に国や自治体が発注する公共事業では、技術士が管理技術者として業務を管理することが求められるケースもあります。
逆に言うと、技術士保有者が会社にいることで仕事を取ってくることができるということになります。
これは、発注者が「専門的知見を持った技術者が関わることによって、品質を担保したい」と考えているためです。
つまり、技術士資格は入札参加のパスポートでもあり、
企業にとっては「技術士をどれだけ抱えているか」が信用力の指標にもなります。



住宅営業や商社の場合は「営業力」で仕事を取ってくるけど、建コン業界ではそれが「技術士」ということなんですね!



そういうことだよ!ほかにもたくさんメリットがあるからどんどん見ていくよ!
② 高度な専門性の証明になる
「技術士」という肩書きは、社会的な信頼を大きく高めます。
この資格は、単に試験に合格しただけの資格ではなく、実務経験に基づく課題解決力・論理的思考・技術提案力が総合的に評価されており、「この人は専門分野の第一線で活躍できる技術者である」という明確な証明になります。
たとえば、同じ説明をしても、「技術士が言うなら信頼できる」という評価を得られるケースも多くあります。
また、社内においても「技術士の意見」として尊重されることが多く、技術的なリーダーシップを発揮しやすくなるのも大きな魅力です。
③ 年収アップ・キャリアアップにつながる
多くの企業では、技術士資格を持っていることで資格手当や昇格の優遇が受けられます。
また、建設コンサルタントやゼネコンでは、部長や所長の資格要件として指定されていることもあり、より責任あるポジションに抜擢されるチャンスが増えます。
実際、技術士を取得したことで、
- 年収が50万円〜100万円以上アップした
- プロジェクトの責任者に昇進した
- とんとん拍子で部長や課長まで昇進した
といった事例も少なくありません。
資格取得がキャリアの転機になることは間違いないでしょう。
技術士の年収事情についてはこちらの記事で詳しく解説しております。
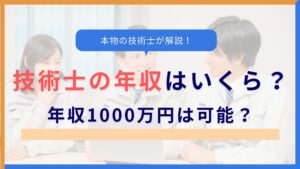
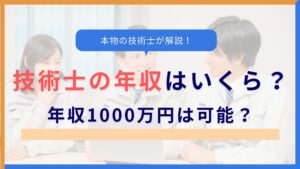
④ 転職・独立に強くなる
技術士は、転職市場でも非常に強い資格です。
特に建設コンサルタント業界では、即戦力人材の証明として高く評価されます。
求人票でも「技術士歓迎」「技術士優遇」と明記されているものが多く、同じ職種でも、資格保有者は高待遇で採用される傾向にあります。
建設コンサルタント業界の転職の流れについて知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。
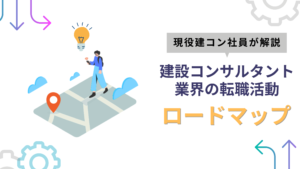
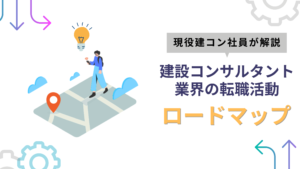
さらに、独立してコンサルタントとして開業することも可能です。
建コン以外でも、下請けの「設計事務所」や「調査会社」などとして独立する方も珍しくありません。



僕の勤めている会社でも技術士を取得して独立した人は何人か見てきたよ!
技術士と他資格との比較


技術系の資格には多くの種類があり、どれも専門性を証明する上で価値があります。
しかし、その中でも「技術士」は一段上の資格として認識されています。
RCCMや土木施工管理技士との違い
まず、建設系の技術者がよく比較対象とするのが、RCCM(シビルコンサルティングマネージャ)や土木施工管理技士です。
これらも重要な国家資格ですが、技術士とは目的や役割が異なります。
それぞれの資格の特徴
| 資格名 | 主な目的 | 対象業務 | 受験資格・特徴 |
|---|---|---|---|
| 土木施工管理技士 | 工事現場の施工管理 | 現場の安全・工程・品質の管理 | 実務経験により受験可。現場管理が中心 |
| RCCM | コンサルタント業務の管理 | 建設コンサルのプロジェクト推進 | 建設コンサル限定の専門資格 |
| 技術士 | 技術全般の専門家認定 | 調査・設計・計画・提案など幅広い技術業務 | 科学技術に基づく最上位の資格 |
土木施工管理技士はゼネコンなどでは必須資格といえますが、建設コンサルタントでは特別なにができるというものはなく、専門性の証明に留まります。
一方、「技術士」と「RCCM」は建設コンサルタントでは入札要件として求められ、非常に重要度の高い資格となります。
実質的なところでは、「技術士」と「RCCM」でできることは大きくは違いがありませんが、入札においては技術士の方が優位に評価されることが多く、事実上の上位互換資格とも言えます。
その他にも建設コンサルタントで役立つ資格はたくさんあります。
こちらの記事で詳しく解説しておりますので併せてご覧ください。
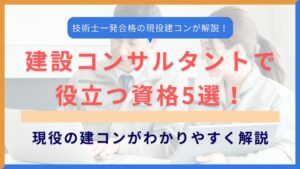
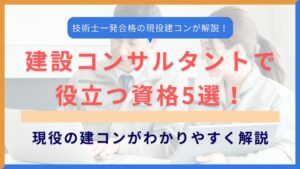
どうすれば技術士になれる?取得の流れをわかりやすく解説


技術士になるには、以下のようなプロセスを辿ることが一般的です。
| ステップ | 内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| ① 学歴・一次試験(または指定課程) | 技術士補(修習技術者)になる資格を得る | ・技術士第一次試験に合格 ・または文部科学大臣指定の教育課程(JABEEなど)を修了 |
| ② 技術士補登録 | 日本技術士会へ登録 | 登録後、正式に「修習技術者」として実務経験を開始 |
| ③ 実務経験 | 第二次試験の受験資格を得る | ・技術士補として4年以上 ・もしくは通算7年以上の実務経験など |
| ④ 第二次試験 | 筆記+口頭試験 | 高度な専門知識・応用力・倫理観を問う試験 |
| ⑤ 技術士登録 | 試験合格後に登録申請 | 日本技術士会への申請で正式な「技術士」に |
| ⑥ CPD(継続研鑽) | 登録後の義務 | 技術の進歩に対応するため、継続的な自己研鑽が必要 |
ステップ① 技術士補になる(一次試験または指定課程)
技術士を目指すための「修習技術者」としての立場であり、技術士の補助業務を通じて実務経験を積むことが目的です。
※「技術士」になるためには必ずしも「技術士補」を取得する必要はありません。詳しくは「ステップ③ 実務経験を積む」をご覧ください。
技術士補になるための2つの方法
| 方法 | 内容 | メリット |
|---|---|---|
| ① 技術士第一次試験に合格 | 技術士会が実施する基礎的試験。年1回実施。 | 学歴に関係なく受験可能(実務未経験でもOK) |
| ② 指定教育課程(JABEE認定課程など)修了 | 文部科学大臣が指定する課程を修了 | 試験免除で「修習技術者」になれる |
※JABEE認定課程修了者は、卒業時に技術士第一次試験が免除されます。
合格または修了後、日本技術士会への登録を経て「技術士補」となります。
ステップ② 技術士補として登録
試験に合格または指定課程を修了しただけでは「技術士補」にはなれません。
日本技術士会への登録手続きが必要です。
登録手順
- 日本技術士会のサイトから登録申請書を提出
- 登録料の納付
- 審査・登録完了
→ 登録完了後、修習技術者証が交付されます。
登録後の役割
- 技術士または優れた指導者のもとで実務経験を積む
- 第二次試験に向けて必要な経験・能力を蓄積



正直なところ、「これができるようになる!」っていうような大きなメリットはないんだよね…。でも、専門性が重要視される業界だから十分に価値はあるよ!
ステップ③ 実務経験を積む(二次試験の受験資格を得る)
第二次試験を受けるには、定められた実務経験年数を満たす必要があります。
| 経歴 | 必要経験年数 | 内容 |
|---|---|---|
| 経歴1 | 技術士補登録後、指導技術士のもとで4年以上 | 技術士の補助としての実務経験 |
| 経歴2 | 技術士補でなくても、優れた指導者の下で4年以上 | 実務の中で技術士相当のスキルを習得 |
| 経歴3 | 学歴等関係なく、通算7年以上の実務経験 | 独立的に技術業務を行っていた場合 |
※大学院修了者は一部の在学期間が経験として認められることもあります。
(例:修士2年=1年分換算)
この「実務経験」は、単なる年数ではなく、技術的な課題解決に携わった内容が問われます。
後の業務経歴票や口頭試験で詳細に説明できるよう、実務記録を残しておくことが重要です。
ステップ④ 技術士第二次試験に挑戦
技術士第二次試験、いよいよ「技術士」になるための試験に挑戦します。
第二次試験は、筆記試験+口頭試験であり、筆記試験合格者のみが口頭試験にチャレンジでき、口頭試験に合格して初めて「技術士」の登録が可能となります。
試験概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 試験形式 | 筆記試験 + 口頭試験 |
| 筆記試験 | 必須科目(600文字×3枚)+選択科目(600文字×6枚) |
| 口頭試験 | 技術士としての実務能力+技術士としての適格性(試問時間20分程度) |
| 実施時期 | 筆記:7月中旬頃、口頭:12月~1月頃 |
| 合格率 | 約10〜15%前後(年度・部門により変動) |



4月に願書提出、最終の合格発表は翌年の3月と1年がかりの資格なんだよ!



休みがなくて大変ですね!僕、頑張れるかな( ;∀;)
ステップ⑤ 登録申請 → 晴れて「技術士」に!
第二次試験に合格した後は、登録申請を行います。
手続き
- 登録先:日本技術士会
- 提出書類:登録申請書、合格証、登録料など
- 登録完了後、「技術士証」が交付され、「技術士(○○部門)」の名称使用が可能に。
これで正式に国家資格「技術士」を名乗ることができます。
ステップ⑥ 登録後の義務:CPD(継続研鑽)
技術士は、資格取得後も最新技術を学び続ける責任があります。
そのため、CPD(Continuing Professional Development:継続的専門能力開発)の実施が求められます。
主な内容
- セミナーや学会への参加
- 専門書の読書・研究
- 社会貢献活動
ポイント
- 年間50時間程度が推奨
- 日本技術士会のマイページから記録可能
- 更新制ではないが、倫理規程上の義務
【総括】技術士はどんな資格?その「すごさ」と資格取得方法
技術士は、単なる資格ではなく、あなたの技術力、経験、そして倫理観を国が保証する技術者の最高峰資格です。取得は容易ではありませんが、手に入れることで、キャリアアップ、年収アップ、そして社会への貢献といった、計り知れないメリットを享受できます。
もしあなたが技術者としてさらなる高みを目指すなら、技術士への挑戦をぜひ検討してみてください。あなたの人生を変えるほどの大きな価値をもたらしてくれるはずです。