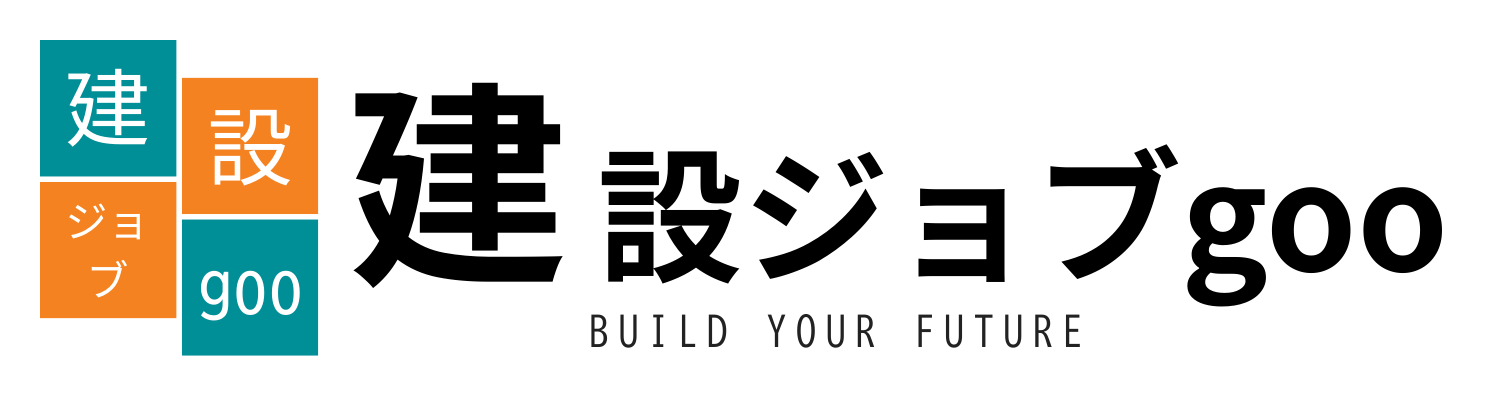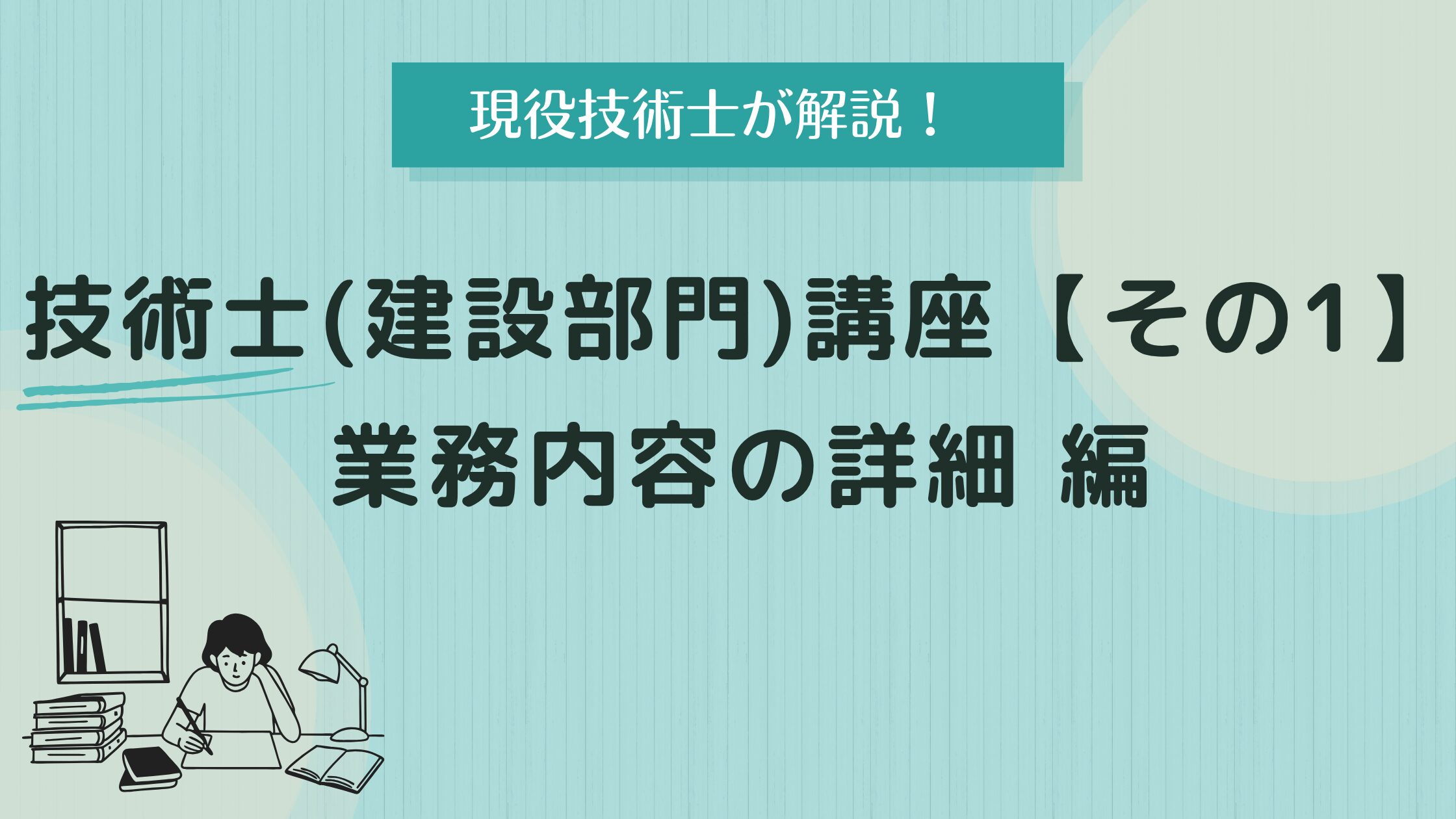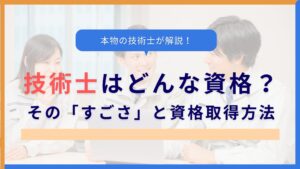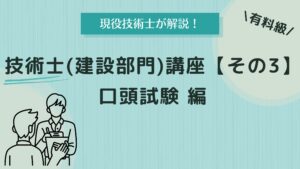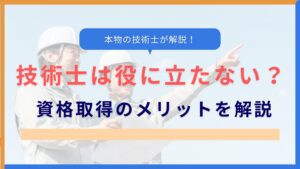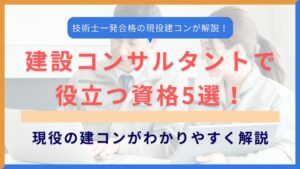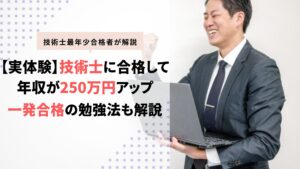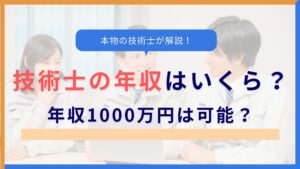新人くん
新人くん願書なんてさっさと終わらせて筆記試験対策に入ろーっと!



ちょっと待ったー!技術士試験の願書はとっても重要なんだ!願書提出時に合否が決まると言っても過言ではないよ!(少し過言かも…
技術士試験の最後の壁である「口頭試験」は、出願書類の経歴書をベースに行われます。
つまり、願書がひどい内容だと100%落ちます!
そうならないために、願書の書き方をしっかり身に着けて、完成度の高い願書を提出しましょう。
\クリックで読みたいところに飛べるよ/
なお、ここでは願書の中でも技術的な部分である「業務内容の詳細」のみについて解説します。
その他については、「技術士第二次試験受験申込み案内」を参考にしてください。
技術士 【業務内容の詳細】の例文


まずは例文を確認してから具体なポイントについて見ていきましょう。
【業務概要】
○○県の中心部において、都市部幹線道路の単純橋梁の架替設計を実施する業務であった。
【立場と役割】
私は主担当技術者として、構造形式検討、詳細設計、関係機関協議等を行った。
【課題及び問題点】
課題①:本橋梁は交通量の多い都市部に位置し、全面通行止めが困難であった。この中、既設橋撤去と新設橋架設を限られた空間で行う必要があり、施工性と安全性を確保しつつ交通影響を最小限に抑えることが課題となった。
課題②:地盤条件が不均一で杭長や支持層が異なり、過大な基礎設計によるコスト増加が懸念された。要求耐震性能を満たしつつ、経済性を確保する合理的設計が求められた。
加えて、交差道路や河川、鉄道など複数の関係機関も存在しており、事業の円滑な進行には、発注者・施工者・関係機関間の調整を図ることが求められた。
【技術的提案】
課題①に対して:鋼単純合成桁+プレキャストRC床版構造を採用し、上部工部材を工場製作とすることで品質の均一化と現場施工の省力化を図った。また、片側交互通行と夜間施工を組み合わせた段階施工を計画し、主要交通の通行確保と安全性を両立した。
課題②に対して:詳細地盤解析に基づく支持層の再評価を実施し、必要な支持力を満たす最適な杭径・本数を設定。杭本数を約15%削減し、施工コスト全体で約10%の縮減を達成した。
また、設計過程では関係機関との調整を主導するとともに、必要に応じて3Dモデルを作成するなどして、円滑な合意形成に努めた。
【成果】
設計成果は発注者から高く評価され、施工時のトラブルなく工期短縮とコスト削減を実現し、地域交通への影響を最小限に抑えた。



この例文をベースに解説していくよ!
技術士【業務内容の詳細】の4つのポイント


口頭試験の前半では、この「業務内容の詳細」をベースに展開されます。
「業務内容の詳細」作成に当たっては必ず口頭試験を意識したものにしましょう。
具体には以下の4つのポイントを意識することが重要です。
- コンピテンシーを盛り込む
- 現場状況が浮かぶ論文にする
- 数値を用いて定量的に示す
- 見やすい文章を意識する
コンピテンシーを盛り込む
技術士試験においては、資質能力(コンピテンシー)が求められます。
求められるコンピテンシーは受験案内に示されており、以下の8つです。
- 専門的学識
- 問題解決
- マネジメント
- 評価
- コミュニケーション
- リーダーシップ
- 技術者倫理
- 継続研さん
参照:公益社団法人 日本技術士会「技術士第二次試験 受験申込み案内」
このうち、口頭試験では③~⑧が問われ、業務内容の詳細を絡めて質問がされやすいのが③~⑥です。
例えば口頭試験では以下のような問われ方をします。
- 詳細記述の業務において、リーダーシップを発揮した点があれば教えてください。
- 詳細記述の業務において、現時点での評価はどのように考えていますか?
どうですか?コンピテンシーを意識せずに書いた文章では答えられませんよね。
もちろん、記載していない事項を回答することは可能ですが、矛盾が生じたりする可能性も高いです。
このため、業務内容の詳細作成に当たっては必ずコンピテンシーを意識してください。
現場状況が浮かぶ論文にする
何度も言っておりますとおり、口頭試験の前半では、「業務内容の詳細」をベースに展開されます。
試験官があなたの720文字を読んで、状況が理解できなければどうなるでしょう。
まずは理解しようとしますよね?
理解するために、現場状況に関する質問を何点かされます。この現場状況に関する質問が増えてしまうと不合格に近づきます。
なぜなら、試験時間は20分(10分間の延長あり)であり、この中でいかに点数を積み上げていくかが重要ですが、このような現場状況に関する質問はいくら回答してもコンピテンシーには関係がないため、ほぼ0点となるからです。
このため、業務内容の詳細では、誰が読んでも現場状況が浮かぶ論文を目指しましょう。
数値を用いて定量的に示す
技術者に相応しく、定量的に示したものが高く評価されます。
理由はシンプルで、評価がしやすいからです。
- A工法を併用することで、大幅な工期短縮を実現した。
- A工法を併用することで、約1か月の工期短縮を実現した。
「大幅」の感覚は人それぞれですし、シチュエーションによっても違ってきますよね。この場合、試験官としては評価がしづらいです。
また、先ほどの現場状況と同様、「大幅とは具体にどのくらいですか?」という無駄な(加点にならない)質問に時間を使ってしまうかもしれません。
このため、実績は可能な限り数値を用いて示すようにしましょう。
見やすい文章を意識する
基本的には当然内容で評価されますが、「読みやすさ」も重要な要素です。
以下のような記号を活用し、箇条書きを取り入れることで、試験官の立場に立った読みやすい文章を心がけましょう。
【】 ①②③… : ・
技術士【業務内容の詳細】の構成


業務内容の詳細は720文字以下で自身の技術的体験を伝える必要があります。
構成は以下のとおりです。あくまで参考ですが、多くの人が似たような構成になるかと思います。
- 業務概要(30~50文字)
- 立場と役割(30~50文字)
- 課題及び問題点(200~300文字)
- 技術的提案(200~300文字)
- 成果(50~100文字)
構成が似通ることは問題ありません。このような構成が求められていますので、独自性を出そうとするのは逆効果です。
業務概要
業務概要は、1文で簡潔に示しましょう。
業務概要では、4つのポイントのうち「現場状況が浮かぶ論文にする」を意識することが重要です。
例文では以下の文章ですが、短い文章に4つのキーワードを入れています。
○○県の中心部において、都市部幹線道路の単純橋梁の架替設計を実施する業務であった。
一つでもかけてしまうと、自分が思い浮かべる現場(実際の現場)と試験官が思い浮かべる現場が一致せず、会話が嚙み合わないということが生じかねません。
立場と役割
立場と役割も同様に、1文で簡潔に示す必要があります。
立場は、必ずしも「管理技術者」などである必要はありません。特に、若いうちは経験が浅いことは試験官も理解してくれています。
変に背伸びをした内容とするのではなく、与えられた立場でしっかり役割を果たしたかが重要になります。
また、役割は課題解決に寄与するものである必要があります。
例えば、課題として橋梁下部工について記載をしているにも関わらず、役割は上部工設計であれば、「課題解決に寄与できていない」となりますよね。
課題及び問題点
大前提として、当然ですが受験する部門・科目に相応しい課題をあげる必要があります。
課題の数としては、1~2つの課題をあげましょう。3つは多すぎます。
そして、課題を正確に認識し、解決につなげていくことが求められます。
また、単純な技術的課題ではなく、制約条件を盛り込むことで、コンピテンシーにも対応しやすくなります。
技術的課題
- 地盤が軟弱で従来工法では施工が困難
- 高水敷に位置するため出水期の施工リスクが大きい
- 都市部で交通規制の影響が大きい
制約条件
- 発注者の強いコスト縮減要求
- 工期短縮と安全確保の両立
- 景観や環境への配慮
技術的提案
上記課題に対する提案・解決策を記載します。
この部分は、いわばあなたの実績となりますので4つのポイントのうち「数値を用いて定量的に示す」ことを意識してください。
また、極端に高度な技術である必要はありませんが、専門分野の応用力を示す必要があります。
課題に対して専門分野を応用した結果、〇%のコスト縮減を実現
といった具合です。
また、課題解決に加えて、調整事項やコミュニケーション方法を記載することで、コンピテンシーへの対応に繋がります。
例文では以下が該当します。
また、設計過程では関係機関との調整を主導するとともに、必要に応じて3Dモデルを作成するなどして、円滑な合意形成に努めた。
成果
最終的にどのような成果が得られたかを簡潔に記載します。
成果は、1文から多くても2文で記載してください。
説得力を高めるには、「課題 → 技術的提案 → 成果」 の一貫性が重要です。
- 課題:「施工ヤードが狭く、作業効率が低下」
- 技術的提案:「プレキャスト部材を採用し、現場作業を最小化」
- 成果:「施工時のトラブルなく工期短縮とコスト削減を実現」
👉 このように、提案と成果が一本の線でつながっているかを意識する必要があります。
特に、試行錯誤を続けるうちに、知らぬ間に一貫性がなくなっていくことが良くありますので気を付けてください。
総括:技術士(建設部門)講座【その1】業務内容の詳細 編
技術士第二次試験の願書「業務内容の詳細」は、単なる業務経歴の紹介ではなく、自分が技術士にふさわしいことを示すプレゼン資料です。
いくら筆記試験を頑張っても、願書がテキトーであれば、4月時点から不合格が決まっています。
一刻も早く筆記試験対策に移りたい気持ちはわかりますが、願書、特に「業務内容の詳細」は丁寧に仕上げましょう。