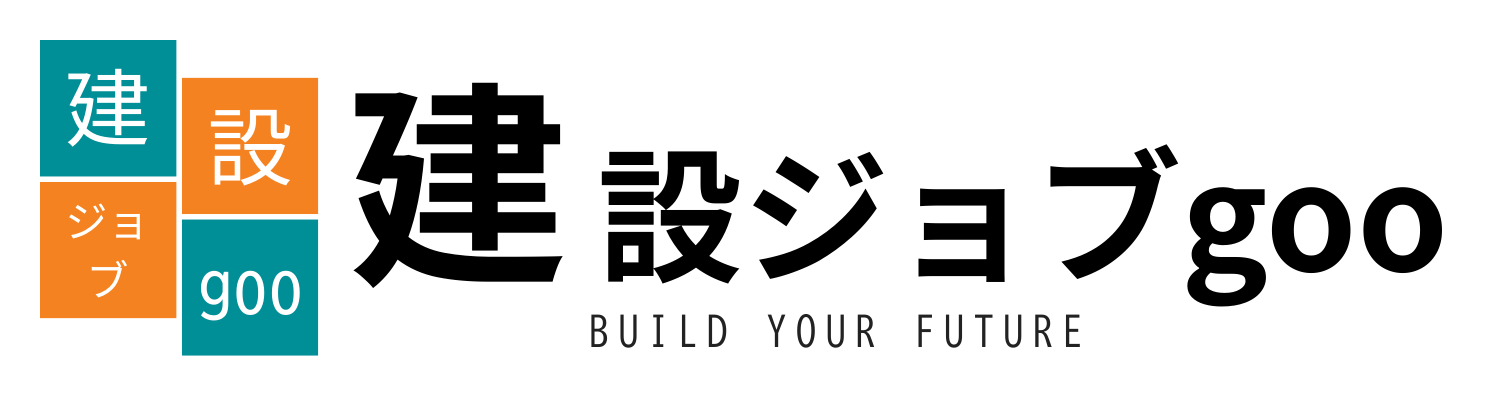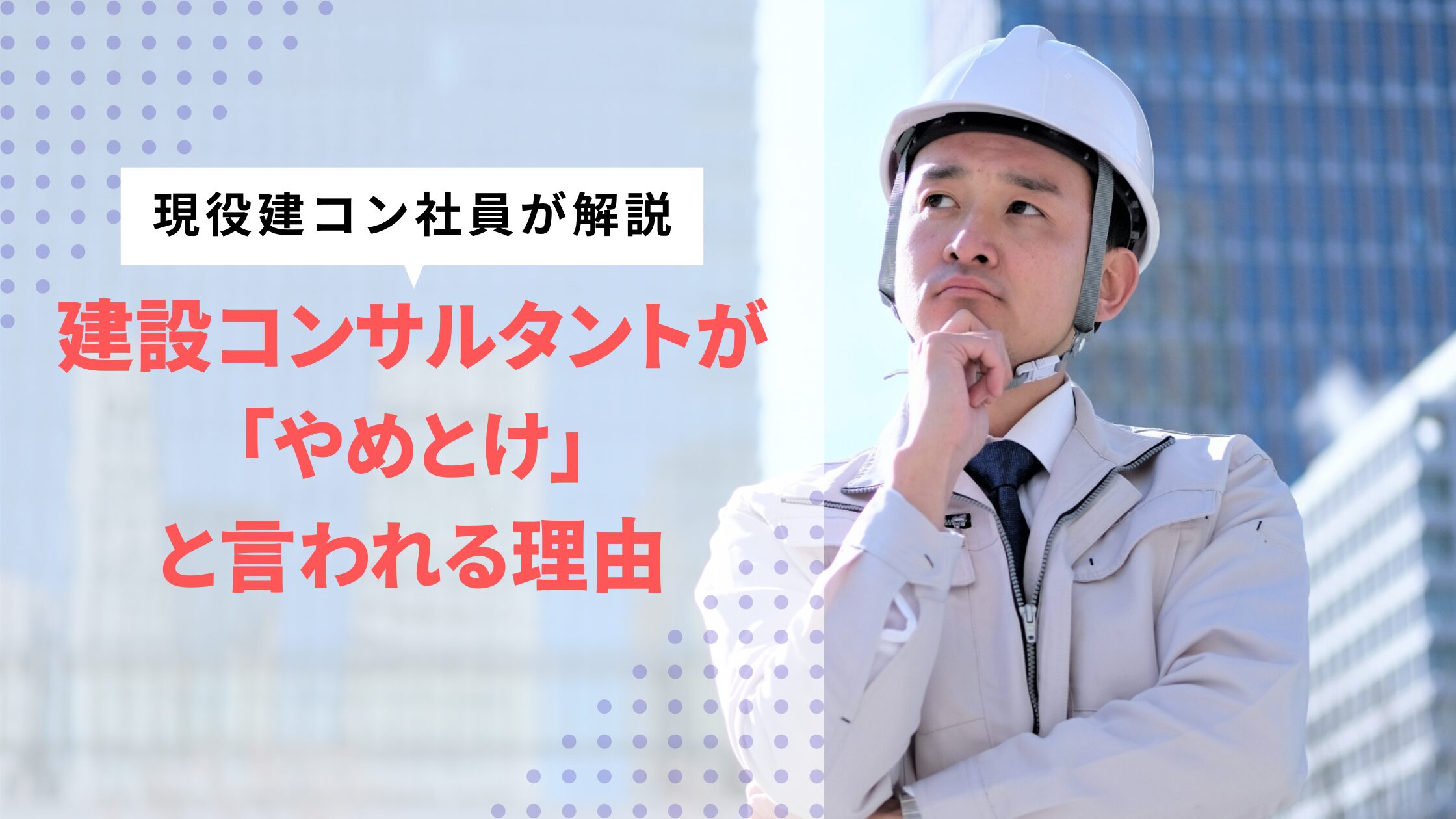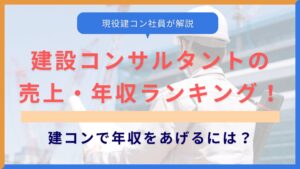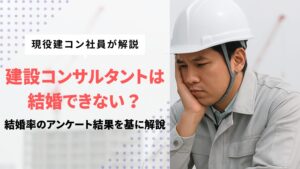「建設コンサルタントは激務でやめとけって聞くけど、本当なの?」
建設コンサルタントへの転職を考えているあなたは、このような不安を抱えているかもしれません。ネットやSNSではネガティブな情報が目につくことも多く、実際のところが気になりますよね。
この記事では、実際に建設コンサルタントとして働く筆者が、「建設コンサルタントがやめとけ」と言われる7つの理由とその実態について解説します。また、社員へのアンケート調査で明らかになった「リアルな声」も紹介。
 ぽむ
ぽむ僕が建コンに6年間務めた実体験だからどこよりも信ぴょう性があるよ!
この記事を読めば、建設コンサルタントの仕事の光と影を客観的に判断できるようになり、「自分にとって本当にこの仕事が合っているのか?」を考えるヒントを得られます。
\クリックで読みたいところに飛べるよ/
建設コンサルタントは「やめとけ」と言われる7つの理由


建設コンサルタントが「やめとけ」と言われる理由は主に以下の7つです。
- 労働時間が長い(残業・休日出勤多)
- 生活リズムが不規則になりがち
- 仕事内容が難しく責任も大きい
- 年功序列で若いうちは収入が低いことも
- 転勤や長期出張が多いことも
- 将来性を危ぶむ声
- 結婚できないとの声



順番にみていくよ!
労働時間が長い(残業・休日出勤多)
建設コンサルタントが「やめとけ」と言われる最大の理由は労働時間の長さにあると言えます。
建設コンサルタント業界では、慢性的な人手不足を抱える企業が少なくありません。そのため、一人ひとりの業務量が増え、必然的に労働時間が長くなります。また、発注者からの急な修正依頼や追加作業、厳しい納期設定などにより、深夜残業や休日出勤が常態化するケースも多く見られます。
特に年度末は、多くの案件の納期が重なるため、最も忙しくなる時期です。この時期は「会社に寝泊まりする」という話も耳にするほど、ハードな働き方になりがちです。



僕は会社で寝泊まりまではしたことないけど、繁忙期には3時間睡眠が何日も続いたことはあったな…。
生活リズムが不規則になりがち
道路や橋梁の点検・調査業務では、交通量が少ない夜間に作業を行うのが一般的です。現場作業が終わると、今度は日中にオフィスでデータの整理や報告書の作成を行います。このような昼夜逆転の生活が続くと、生活リズムが崩れて体調を崩しやすくなります。
さらに、台風や地震などの災害時には、緊急の現地調査を求められることも。予定が大きく狂うため、プライベートな時間を確保することが難しくなる点も、やめとけと言われる一因です。
仕事内容が難しく責任も大きい
建設コンサルタントの仕事は、専門性が非常に高い分野です。構造物の設計や河川の計画、地質調査など、専門知識がなければ成り立ちません。また、手掛けるのは人々の生活を支える社会インフラ。一つでもミスがあれば、人命に関わるような大事故につながる可能性もあります。そのため、「失敗が許されない」という強いプレッシャーが常にのしかかります。
精神的な負担に加え、技術士やRCCMといった難関資格の取得がキャリアアップに不可欠なため、仕事と並行して資格勉強を進めるプレッシャーもあります。
年功序列で若いうちは収入が低いことも
経験と実績が重視される業界であるため、年功序列が色濃く残っている企業が多くあります。ベテランになれば高収入を得られますが、20代のうちは、家賃光熱費などの必要経費を支払うともう余裕がないということも珍しくありません。



仕事していないのに僕より給料が高いおじさんもいっぱいいたよ!怒
ただし、技術士などの国家資格を取得すれば、専門家として早期に評価され、昇進や昇給に繋がることが多いです。若手でも積極的にキャリアアップを目指せる道はあります。
転勤や長期出張が多いことも
全国規模の案件を受注する大手企業では、数ヶ月単位の長期出張が発生することも珍しくありません。また、全国に支店を構える企業では転勤も頻繁に発生します。プロジェクトごとに勤務地が変わることもあり、落ち着いて生活するのが難しいと感じる人もいます。
特に家族を持つ人にとっては、単身赴任や引っ越しが大きな負担となりやすいでしょう。一方で、地域密着型の中小企業では、転勤がほとんどないこともあります。
将来性を危ぶむ声
「防災、減災・国土強靭化のための5か年加速化対策」が令和7年度に終了することなどから、建設コンサルタントの業務は縮小傾向にあります。その他、AIやDXの発展などが懸念され、将来的に仕事がなくなるのではないかと懸念する声もあります。
建設コンサルタントの将来性については、「建設コンサルタントはなくなる?業界の現状と将来性を徹底解説」でさらに詳しく解説しておりますので併せてご覧ください。
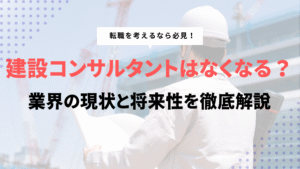
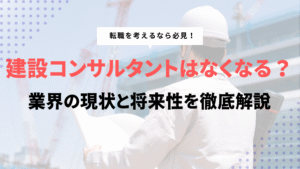
結婚できないとの声
労働時間の長さや不規則な生活から、「仕事が忙しくて出会いの場がない」「家庭との両立が難しい」といった理由で、結婚できないと言われることもしばしばあります。
業界の特徴として男性が大半をしめるということもあり、職場での出会いが少ないことも影響している言えます。



男女比に関するデータはないみたいだけど、僕の勤めている会社では8割以上は男性だよ!
しかし、近年は働き方改革を推進する企業も増えています。プライベートの時間を確保しやすくなっています。リモートワークやフレックスタイム制を導入する企業も少しずつ増えており、今後は働きやすさが改善されていくと期待できます。
建設コンサルタントのギャップ・退職理由【アンケート結果】
建設コンサルタントの実態をより深く知るために、筆者が前職で勤めていた建設コンサルタント会社で、社員へのアンケート調査を実施しました。
ここでは、「入社前後のギャップ」と「退職理由」について、現場のリアルな声をデータでお伝えします。
【前提条件】
- 地方密着型の中小企業
- 対象人数
- 入社前と退職後のギャップ:16名(うち女性3名)
- 退職理由:15名(うち女性22)
- 調査方法:口頭による聞き取り調査
- ※注意点 このアンケート結果は、あくまで一社のデータであり、建設コンサルタント業界全体の傾向とは異なる可能性があります。しかし、一つの会社のリアルな実情として、参考になる部分も多いのではないでしょうか。
入社前と入社後のギャップ【アンケート結果】



入社前と入社後のギャップのアンケート結果は以下のとおり!
入社前後のギャップ アンケート結果
| 順位 | ギャップの内容 | 人数(女性の人数) | パーセンテージ |
| 1位 | 想像よりも忙しい・休暇が取れない | 5名(0名) | 31.3% |
| 2位 | 仕事内容が幅広い・勉強することが多い | 4名(0名) | 25.0% |
| 3位 | 学歴や学生時代の研究内容はそこまで関係ない | 2名(1名) | 12.5% |
| 4位 | 意外と現場作業が多い | 2名(1名) | 12.5% |
| 5位 | 細かい作業が多い | 1名(1名) | 6.3% |
| 5位 | 自由度が高い(自分の思い通りの設計にできることも多い) | 1名(0名) | 6.3% |
| 5位 | 特になし | 1名(0名) | 6.3% |
入社前後のギャップについて聞いた結果、最も多かったのは「想像よりも忙しい・休暇が取れない」という回答でした。多くの人が、入社前に想像していた以上に業務量が多く、プライベートの時間を確保するのが難しいと感じているようです。
また、意外な声として「学歴や学生時代の研究内容はそこまで関係ない」という回答も挙がりました。これは、実務に入ると座学の知識だけでなく、現場対応力やコミュニケーション能力など、幅広いスキルが求められることや勉強と実務の内容が必ずしも直結しないことなどを意味します。



逆に考えると、「学生時代にそれほどのすごい経験がなくてもがんばっていける」ともとれるよね。
退職理由【アンケート結果】



続いては退職理由についてのアンケート結果だよ!
退職理由 アンケート結果
| 順位 | 退職理由 | 人数(女性の人数) | パーセンテージ |
| 1位 | 労働時間が長い | 4名(1名) | 26.7% |
| 1位 | 向いていない・他にやりたいことがある | 4名(0名) | 26.7% |
| 3位 | 人間関係(社内外問わず) | 2名(1名) | 13.3% |
| 3位 | 体調不良 | 2名(0名) | 13.3% |
| 3位 | 地元に帰る | 2名(0名) | 13.3% |
| 6位 | フルリモートのところで働きたい | 1名(0名) | 6.7% |
退職理由では、「労働時間の長さ」と「向いていない・他にやりたいことがある」が同率1位という結果になりました。
労働時間については、やはり多くの人が働き方に課題を感じていたことがわかります。「向いていない・他にやりたいことがある」という回答は、入社前のイメージと実際の仕事内容とのミスマッチが退職の大きな要因となっていることを示唆しています。
建設コンサルタントの残業が多い4つの理由


アンケート結果より、「労働時間の長さ」が、建設コンサルタントのネガティブ要因になっていることがわかりました。では、この労働時間の長さの理由は何なのでしょうか?
それは主に以下の4つです。
- 顧客からの無理な納期や指示
- 年度末や年末に工期が集中する
- 現場対応やミスがあった時の対応に追われる
- 落札競争が激しい



これも順番に見ていくよ!
顧客からの無理な納期や指示
建設コンサルタントの仕事は、顧客(発注者)である国や自治体、民間企業との協力関係が不可欠です。しかし、発注者からの急な仕様変更や追加作業の依頼は珍しくありません。厳しい納期を突きつけられたり、想定外の指示を受けたりすることも多々あります。
こうした無理な要求を断ると、次の案件を受注する際に不利になる可能性があるため、ある程度の無理は受け入れざるを得ないのが実情です。結果として、作業量が急増し、長時間労働につながってしまいます。
年度末や年末に工期が集中する
建設コンサルタントが手掛ける業務のほとんどは、公共工事です。公共工事は国の予算執行の都合上、年末から年度末にかけて工期が集中する傾向にあります。
また、民間工事と異なり、公共工事は工期を1日でも遅らせることが原則として認められません。もし工期を過ぎてしまう場合は、工期延伸の手続きが必要となりますが、特別な理由がない限り認めてはもらえません。そのため、この時期は徹夜や休日出勤が当たり前となり、業務のピークを迎えます。



もちろん民間事業にも大変なことは多いけど、工期の点に関しては確実に公共事業が厳しい…。
現場対応やミスがあった時の対応に追われる
建設コンサルタントの業務は、①受注→②設計→③納品→④工事という流れであり、基本的に①~③で形上は業務が完了し、支払いまで行われますが、実際に工事に入ってからが非常に大変です。
自然を相手にする工事であるため、調査をしてから設計を行うとはいえ、設計と現場で差異がでることも多くあり、現場対応に非常に苦労します。また、設計ミスが発覚した時が特に大変です。
設計時に入念にチェックを行うものの、人間が設計する以上、100%完璧ということはありえません。ミスがあった場合、工事の際に発覚し、修正作業に追われるということが珍しくありません。



通常の業務は工程が読めるからまだいいんだけど、現場対応は予期せぬところに飛び込んでくるから予定が狂って残業が増えちゃうんだ…。
落札競争が激しい
公共事業の入札では、最も低い価格を提示した業者が受注する一般競争入札が主流です。業界全体の案件数が減少傾向にある近年、受注競争はさらに激化しています。
この厳しい競争の中で、企業は安価で案件を受注せざるを得ません。結果として、利益率を保つために一人で複数の業務をこなしたり、少ない人員で案件を進めたりする必要が出てきます。これが、社員一人ひとりの人員リソースに余裕がなくなり、長時間労働を招く要因となっています。
建設コンサルタントが向いていない人と本当の【魅力】
続いては、これまでの内容を踏まえて、以下の3つについて見ていきます。
- 建設コンサルタントに向いていない人はどんな人か
- 建設コンサルタントの魅力
- 建コンのホワイト企業の探し方
建設コンサルタントに向いていない人


これまでの内容から、建設コンサルタントの仕事には厳しい側面があることが見えてきました。では、具体的にどのような人がこの仕事に向いていないのでしょうか。
ワークライフバランスを最優先したい人
建設コンサルタントは、工期の都合や突発的なトラブル対応により、労働時間が長くなりがちです。趣味や家族との時間を第一に考えたい人にとっては、この働き方は厳しいと感じるかもしれません。
もちろん、業界全体が働き方改革に取り組んでおり、労働環境が改善されつつあるのも事実です。しかし、根本的な労働時間の長さは、この仕事の特性上避けられないことが多いです。
ただ、建設コンサルタントにも残業が少なく、働きやすいホワイト企業は存在します。ホワイト企業の見極め方については、「建設コンサルタントのホワイトランキング|失敗しない【見分け方】」で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。


体力・精神的なタフさに自信がない人
建設コンサルタントの仕事は、デスクワークだけではありません。昼夜を問わない現場での調査や点検、厳しい気象条件の中での作業など、体力的な負担も大きいです。
また、人の命に関わるインフラを扱うため、工期のプレッシャーや、万が一ミスがあった場合の精神的なプレッシャーも相当なものです。顧客からの厳しい指摘や、責任の重さに耐えられる精神的なタフさも求められます。
資格勉強やスキルアップに時間を割きたくない人
この業界では、常に最新の技術や法規を学び続ける必要があります。実務を通してのOJTはもちろん、技術士やRCCMといった専門資格の取得もキャリアアップには不可欠です。
そのため、仕事が終わった後も勉強時間を確保するなど、成長意欲が低い人には、この仕事は向いていません。「学び続けること」を楽しめる人こそ、この仕事で成功できるでしょう。
細かな作業が苦手な人
構造計算や数量計算など、建設コンサルタントの業務には緻密な数字を扱う作業が数多く含まれます。わずかなミスが大きな問題につながるため、入念なチェックが欠かせません。
たとえば、赤黄チェック(赤ペンと黄色ペンで間違いがないかを確認する作業)や照査技術者による照査など、何重ものチェック体制が取られています。そのため、「細かい作業は苦手」という人にとっては、ストレスを感じやすいかもしれません。
辛いだけじゃない!建設コンサルタントの【魅力】


ここまで「やめとけ」と言われる理由を解説してきましたが、建設コンサルタントの仕事には、それを上回るほどの大きな魅力があります。この仕事でしか得られない、かけがえのないやりがいについて見ていきましょう。
みんなの暮らしを支える仕事
建設コンサルタントの仕事は、道路、橋、河川、上下水道など、人々の生活に欠かせない社会インフラを支えています。普段、何気なく使っている公共施設やインフラは、すべて誰かが設計し、整備したものです。
自分の手掛けたプロジェクトが、災害から地域を守ったり、人々の暮らしを便利にしたりする様子を目の当たりにできるのは、この仕事ならではの醍醐味。大きな社会貢献性を感じられるため、日々の激務を乗り越える大きなモチベーションになります。
地図に残る仕事
自ら設計した構造物が、地図に残るのも建設コンサルタントの魅力です。何十年、何百年と形として残り続ける橋や道路を見ると、大きな達成感と誇りを感じられます。
業務の管理技術者として携われば、設計した構造物の銘板(めいばん)に自分の名前が刻まれることもあります。将来、子どもや孫に「この橋はお父さんが設計したんだよ」と誇らしげに話せるような、ロマンのある仕事です。



自分で初めて設計した橋が完成したときは本当に感動したのを今でも覚えてるよ!
手に職をつけられる
この業界は、高度な専門知識と技術が求められます。そのため、一度身につければ一生ものの専門スキルとして通用します。特に、技術士やRCCMといった国家資格を取得すれば、専門家としての市場価値は飛躍的に高まります。
特に技術士は、科学技術分野における最高峰の国家資格であり、取得が非常に難しいことで知られています。この資格を持っているだけで、転職市場では引く手あまたの人材となり、キャリアの選択肢が大きく広がります。



技術士取得前と後の両時期に転職活動をしたからわかるけど、面接官の対応も明らかに違ったよ!笑
年収が高い
専門性が高く、責任が重い仕事であるため、建設コンサルタントは年収が高い傾向にあります。
厚生労働省が発表した「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、建設コンサルタントが含まれる「技術サービス業(他に分類されないもの)」の平均年収は約401.8万円です。これは、同調査による日本の平均年収である約330.4万円を大きく上回る金額です。
また、資格手当や役職手当が充実している企業も多く、実務経験を積み、技術士などの資格を取得することで、さらに高収入を目指すことが可能です。
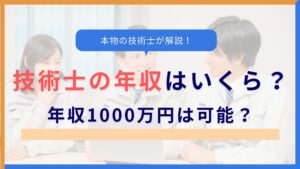
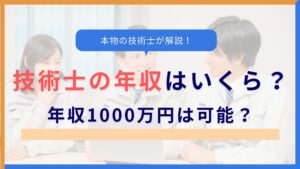
建設コンサルタントのホワイト企業に転職する方法
「建設コンサルタントの仕事は魅力的だけど、やっぱり激務は避けたい…」
そう考えるなら、働きやすいホワイト企業への転職を目指しましょう。ホワイト企業への転職を成功させるには、求人サイトだけでは得られない情報を活用することが不可欠です。



求人情報はオブラートにオブラートを重ねた「ほぼ嘘」と言ってもいいような情報も多いから本当に注意だよ!
ホワイト企業への転職を成功させるなら、転職エージェントの利用が必須です。転職エージェントは、建設コンサルタント業界に精通しており、求人サイトには掲載されていない非公開求人を多数保有しています。
また、企業の内部情報に詳しいため、求人票だけではわからない「実際の残業時間」や「職場の雰囲気」なども事前に教えてもらえます。これにより、入社後のギャップを最小限に抑えることが可能です。
【総括】建設コンサルタントが「やめとけ」と言われる理由|現役建コンが解説
建設コンサルタントは「やめとけ」と言われる厳しい側面がある一方で、社会貢献性の高さ、地図に残る仕事、高い年収など、他の仕事にはない大きな魅力も持っています。
労働時間の長さや責任の重さなど、この仕事の厳しさは事実です。しかし、働き方改革を進める企業も増えており、自分に合った企業を選べば、仕事のやりがいとプライベートの両立も可能です。



僕も「ブラック建コン」から「ホワイト建コン」への転職に成功したひとりだよ!
「建設コンサルタントに挑戦してみたい。でも失敗はしたくない…」
そう考えているなら、自分にぴったりのホワイト企業を見つけるのが最善の道です。あなたのスキルや希望に合った企業はきっと存在します。