建設コンサルタント業界は、社会インフラを支えるやりがいの大きな仕事である上、給与水準も高く人気のある職種です。
その一方で、「残業が多い」、「有給がとりにくい」、「離職率が高い」などの問題を抱えているのも現実であり、よく調べてから転職しなければ、転職先がブラック企業ということも珍しくありません。
また、建設コンサルタントで働いている方の多くは長時間労働の中、一度は転職が頭をよぎったことがあるのではないでしょうか。
転職するならホワイト企業がいいけど、建設コンサルタントの「ホワイト企業」ってどこ? と気になりますよね。
この記事では、「建設コンサルタントでホワイト企業に転職したい!」と考えている方に向けて、離職率や年収、ワークライフバランスなど、さまざまな視点から厳選したホワイト企業ランキングを紹介します。
さらに、ランキングだけではわからない「本当に自分に合ったホワイト企業」を見つけるための簡単な見分け方や、ブラック企業を回避する方法についても、私自身の転職経験を踏まえて詳しく解説していきます。
 ぽむ
ぽむ建設コンサルタントは、業界全体の傾向として労働時間が長い傾向にあり、離職率も高く、近年では改善傾向にあるものの、いまだに「ブラック」と言われる企業も多く存在するのが現実なんだ…。今回は、そんな建設コンサルタント業界からホワイト企業を見抜くポイントなどを解説していくよ!
\クリックで読みたいところに飛べるよ/
転職を決意した方も、転職しようか迷っている方も人生相談がてら、完全無料でプロのサポートを受けてみませんか?


リクルートエージェントが選ばれる理由
- 転職支援実績No.1!
- 完全無料(登録~内定~入社まで費用0円)!
- 応募書類添削・面接対策・業界情報収集など手厚いサポート!
- 圧倒的な求人数(公開求人60万件/非公開求人40万件)!
- 全国対応!
\ 完全無料でプロの転職サポートが受けられる /
建設コンサルタントのホワイト企業ランキング



まずは、建設コンサルタント業界のホワイト企業をランキング形式で紹介するよ。今回は、実際にその企業で働いていた社員の口コミ評価をベースにしたランキングと、業界全体の働き方の特徴を解説していくよ!
建設コンサルタントのホワイト企業ランキングTOP5(口コミ評価ベース)
今回は、国内最大級の社員クチコミサイトである「OpenWork(https://www.openwork.jp/my_top)」の評価を参考に、建設コンサルタント業界のホワイト度ランキングを作成しました。
このランキングは、「社員の士気」「風通しの良さ」「法令順守意識」といった複数の項目から算出される「ホワイト度」の総合評価が高い企業を厳選しています。
評価は「待遇の満足度」「ワークライフバランス」「社員の士気」「成長環境」などを総合したスコアです。
| ランク | 企業名 | OpenWork総合スコア | 平均残業時間 | 有休取得率 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 日本工営 | 3.66 | 38.5h/月 | 約60.6% | 業界最大手。海外プロジェクト多数。給与水準高め。 |
| 2位 | パシフィックコンサルタンツ | 3.72 | 41.9h/月 | 約60.8% | インフラ系に強い。近年は働き方改革を推進。 |
| 3位 | 八千代エンジニヤリング | 3.57 | 40.0h/月 | 約61.8% | 中規模ながらバランス型。女性活躍推進。 |
| 4位 | 建設技術研究所 | 3.90 | 40.3h/月 | 約58.7% | 公共事業に強み。比較的安定志向。 |
| 5位 | オリエンタルコンサルタンツ | 3.32 | 49.2h/月 | 約50.0% | 海外案件あり。成長機会は多いが繁忙期は激務。 |
※スコア・残業時間・有休率はOpenWorkなどの公開情報をもとにした参考値
もちろん、口コミは個人の主観が反映されるため、あくまで参考程度にしてください。ただし、多くの社員が同じような評価をしている場合、その傾向は信憑性が高いと言えます。
建設コンサルタントの特徴
冒頭でも触れたように、建設コンサルタント業界全体としては、いまだに「ブラック」と言われがちな特徴を持っています。具体的な特徴を見ていきましょう。
残業時間が長い
建設コンサルタントの中には、残業が常態化している企業も少なくありません。 国土交通省の調査(令和元年度)によると、建設コンサルタント企業の年間総実労働時間は平均2,000時間以上(出典:国土交通省|建設業を取り巻く現状と課題)であり、これは他産業と比べて長い傾向にあります。
これには以下のような理由があります。
建設コンサルタントの残業時間が長い理由
無理な納期や指示
発注者からの無理な納期や、急な仕様変更など、突発的な業務が発生しやすいことがあげられます。断ることで、次の仕事に影響が出るため、多少の無理難題であれば、引き受けざるを得ないというのが現状です。
年度末や年末に工期が集中する
建設コンサルタントの顧客は公共機関がほとんどを占めており、予算の関係上、年末や年度末に工期が集中します。そのため、年末や年度末が繁忙期となり、この時期が特に残業が多くなります。
現場対応・ミスがあったときの対応に追われる
建設工事はざっくり、「①調査→②計画・設計→③工事」という流れであり、建設コンサルタントの業務としては②あるいは①と②が該当します。表面上は②が終われば業務は完了ですが、③の工事が終わるまで油断ができません。設計にミスがあった場合や施工ができない場合には修正作業に追われることも珍しくないからです。
落札競争が激しい
建設コンサルタントの業務は、価格競争が非常に激しく、発注者が想定する予定価格を大きく下回ることが珍しくありません。これは、落札会社の利益が減少することを意味します。このため、利益を確保するために複数の業務を受注する必要があり、長時間労働に繋がっています。
建設コンサルタントの残業事情については、「建設コンサルタントが「やめとけ」と言われる理由|現役建コンが解説」でさらに詳しく解説しておりますので、参考にしてください。


有給休暇の取得率が低い
上記の理由に起因して、有給休暇の取得率も他産業と比較して低い傾向にあります。 ただし、近年では有給休暇の取得が義務化されたこともあり、改善傾向にあります。
年功序列が多い
業界全体として、長年培ってきた技術力や経験が重視される傾向が強く、年功序列の風土が根強く残っている企業が多く見られます。 若手社員のうちは、成果を出しても給与が上がりにくいと感じるかもしれません。
男性が8割以上
かつては男性の比率が圧倒的に高かった業界であり、現在でも8割以上を男性が占めています。 しかし、近年は女性の技術者やコンサルタントも増加しており、女性が活躍できる環境づくりに力を入れている企業も増えています。
このように、建設コンサルタント業界は、全体的に「ブラック企業」特有の特徴が目立つ側面があります。 しかし、これらはあくまで「業界全体の傾向」です。後ほど詳しく解説しますが、近年では働き方改革が急速に進んでおり、これらの傾向を改善している「ホワイト企業」も確実に増えています。
建設コンサルタントのホワイト企業とブラック企業の違いは?



建コンのホワイト企業ランキングや建コンの特徴がわかったところで、続いては、ホワイト企業とブラック企業の見極め方について見ていこう!
建設コンサルタントにおけるホワイト企業の見極めポイント
前述のランキングはあくまで参考です。本当に自分に合ったホワイト企業を見つけるためには、求人情報や口コミに書かれていない「本質的な見極めポイント」を知っておくことが重要です。
ここでは、私が転職活動を通して見出した、建設コンサルタント業界のホワイト企業に共通する5つのポイントを解説します。
離職率が低い・平均勤続年数が長い
ホワイト企業を見極める上で、最も確実な指標の一つが「離職率」です。社員が定着している会社は、働きやすい環境が整っている可能性が非常に高いと言えます。
筆者が以前勤めていた建設コンサルタント会社では、30人規模の部署で毎年3〜5人ほどの離職者が出ていました。特に5〜6年目の、ようやく一人前になりかけてきた中堅層が辞めていくことが多く、結果として若手社員やベテラン社員への負担が増え、忙しさが減らないという悪循環に陥っていました。
一方で、現在勤めている会社では、ここ5年ほど離職者がゼロであることから、中間層も育っており、その結果一人当たりの労働時間も減り、さらに離職者が減るという好循環となっています。
業界全体の平均離職率は明確なデータはありませんが、厚生労働省の「雇用動向調査(出典:厚生労働省|令和4年 雇用動向調査結果の概要)」によると、日本の産業業全体の離職率は約15%前後で推移しています。これに対し、5%程度の離職率であれば「ホワイト企業」と判断できるでしょう。 離職率や平均勤続年数は、企業の公式サイトや採用ページに記載されていることが多いですが、面接時に直接質問することも有効です。
残業時間が短い・休暇日数が多い
ホワイト企業は、社員のプライベートを尊重します。その証拠となるのが「残業の少なさ」と「休暇の多さ」です。
建設コンサルタント業界の転職サイトに記載されている残業時間は、月20〜30時間とされていることが多いです。しかし、この数字はパート・契約社員なども含めた平均値だったり、サービス残業が含まれていなかったりする場合があるため、鵜呑みにするのは危険です。 実際には、月45時間以上の残業が常態化している会社も少なくありません。
目安としては、残業時間が月20時間未満、有給休暇取得率70%以上、年間休日120日以上であれば、十分にホワイト企業と言えるでしょう。
「年間休日120日以上」「完全週休2日制」は多くの企業が謳っていますが、実態は会社説明会や面接で担当者に直接確認することをおすすめします。仮に質問して落とされるようであれば、その会社は残業が多い、つまりブラック企業である可能性が高いため、恐れずに入社前に必ず確認しておきましょう。
大手企業ほど残業が多い傾向
「大手=ホワイト」と考えがちですが、建設コンサルタント業界においては大手企業ほど激務になる傾向(一概には言えませんが)があります。 大手には国や都道府県の重要なプロジェクトが集中するため、仕事量が多くなりがちです。また、多くの案件を同時に抱えるため、管理職やベテラン社員に大きな負荷がかかることも少なくありません。
もちろん大手でも働き方改革は進んでいますが、仕事量が圧倒的に多いため、中小企業と比較して残業時間は長くなる傾向にあります。 地方の中小企業は、地域に根差した安定した案件が多く、激務になりにくいというメリットもあります。
ただ、もちろん一概には言えないうえ、中小企業は資金力が弱いことから、大手に比べて技術の導入が進んでおらず非効率であるが故、仕事量は少ないが残業が多くなるということも珍しくはありません。
育休取得・フレックスが充実
社員が多様な働き方を実践できる環境が整っていることも、ホワイト企業を見極める重要なポイントです。 例えば、育児休業の取得実績や、フレックスタイム制の導入状況などが挙げられます。
最近では、男性社員でも1年間の育児休業を取得できる会社も増えてきました。一方で、ブラック企業では「育休って何?フレックスって何?」といった認識が薄かったり、たった一人でも育休を取るとプロジェクトが回らなくなったりする状況も珍しくありません。
柔軟な働き方を認めている会社は、社員の事情を考慮する風土が根付いている証拠であり、働きやすい環境が期待できます。
ホワイト企業ランキングをあてにしすぎない方が良い理由
ここまでランキングや見分け方を解説してきましたが、ランキングを鵜呑みにしない方が良い理由が3つあります。
- 支店によって天と地の差がある:大手企業の場合、全国に支店があるため、配属される部署や上司によって労働環境が大きく異なります。面接時には、希望の配属先に行けるか、その部署の状況はどうか、転勤の可能性はあるかなどを必ず確認しましょう。
- 転職サイトの残業時間は実態と異なることが多い:前述の通り、掲載されている残業時間はあくまで目安です。サービス残業や持ち帰り仕事がある可能性も考慮しましょう。
- 地方企業はランキングに出てこない:ランキングは主に全国展開している大手企業が中心となりがちです。しかし、地方の優良な中小企業はランキングに載らないことがほとんどです。地元での転職を考えている場合は、ランキング以外の情報収集も重要です。
建設コンサルタントにおけるブラック企業の特徴・回避方法
ホワイト企業の特徴を知ることは、ブラック企業を回避することにも繋がります。ここでは、転職活動中に見極めるべきブラック企業の特徴と、それを回避するための具体的な方法を、私の実体験も交えながら詳しく解説します。
求人票や会社の情報からわかるブラック企業の特徴
求人票は企業の顔ですが、中には実態と異なる情報を載せている場合があります。以下の点に注意して求人情報を確認しましょう。
- 給与や残業代に関する記載が曖昧:「実績に応じて」「頑張り次第で」といった具体的な金額が明示されていない場合や、「みなし残業」の時間が極端に長い場合は注意が必要です。筆者の友人の会社では「みなし残業代45時間分を含む」とありましたが、実際にはそれを超える残業が常態化していました。
- 常に求人が掲載されている:慢性的に人手不足であることの裏返しであり、離職率が高い可能性があります。
- 福利厚生が充実しているように見えて実態がない:「資格取得支援制度」「研修制度」などと書かれていても、実際にはそのための時間や費用が捻出されず、形骸化しているケースも少なくありません。
- 企業規模の割に中途採用の募集が多い:大手企業でも、常に複数の職種で中途採用を募集している場合は、退職者が多い可能性を疑いましょう。
面接でわかるブラック企業の特徴
面接は企業から評価される場であると同時に、こちらが企業を評価する貴重な機会です。面接官の言動から、その会社がブラックかどうかを見抜くことができます。
- 面接官が威圧的、横柄:面接は、その会社の社員の雰囲気や文化を映す鏡です。高圧的な態度や、質問に対して明確な回答を避ける面接官は、社員が尊重されていない環境を示唆している可能性があります。
- 労働時間や残業について質問すると言葉を濁す:「プロジェクトによる」「人によって違う」といった回答でごまかされる場合、実態は「聞くに堪えないほど残業が多い」可能性が高いです。筆者の経験上、本当にホワイトな会社は、残業時間や有給取得率について具体的な数値を交えて堂々と答えてくれます。
- 会社のネガティブな質問に不機嫌になる:離職率やサービス残業の有無など、聞きにくい質問をした際に、明らかに不機嫌になったり、質問を遮ったりする場合は、やましいことがある証拠です。
失敗しない建設コンサルタントの【転職ロードマップ】



↓これまでの内容を踏まえて、転職活動はこんな感じで進めていくよ↓
- 転職エージェントに登録
- 自己分析(強みややりたいことの洗い出し)
- 書類作成(履歴書・職務経歴書)
- 応募
- 面接
- 条件交渉
- 退職→入社



一緒に詳しく見ていこう!
建設コンサルタントの転職は、闇雲に進めても良い結果は得られません。成功の鍵は、自分自身の強みを理解し、計画的に行動することにあります。ここでは、私が実際に転職を成功させた際にたどった「転職ロードマップ」の概要をご紹介します。
失敗しない建設コンサルタントの【転職ロードマップ】
建設コンサルタントへの転職を考えるなら、転職エージェントの活用は必須です。彼らはあなたの転職活動を強力にサポートしてくれる心強い味方です。
- 聞きにくい会社の裏事情を聞いてもらえる: 転職エージェントは企業の人事担当者と頻繁にやり取りしているため、求人票には載っていない実際の残業時間や離職率、職場の雰囲気といった裏事情にも詳しいことが多いです。自分では聞きにくいことも、エージェントを介せばスムーズに確認してもらえます。そもそも、長年の取引がある企業については、エージェントが独自のネットワークで詳細な情報を把握していることが多いです。
- 書類作成や面接対策、条件交渉を完全代行: 履歴書や職務経歴書の添削、面接日程の調整、年収や入社日などの条件交渉まで、面倒な手続きをすべて代行してくれます。プロの視点からあなたの強みを最大限に引き出す書類を作成したり、面接での受け答えを一緒に考えたりしてくれるため、選考通過率が格段に上がります。
- 完全無料: 転職エージェントは、企業から採用成功報酬を得る仕組みのため、求職者は一切費用をかけずにサービスを利用できます。
【注意点】 エージェントは転職成立で初めて報酬を得るため、やみくもに転職させようとするエージェントもいるのが現実です。そのためエージェント選びは超重要です。
職活動で最も重要なのは、この自己分析のステップです。「なぜ転職したいのか?」という問いに明確に答えられないと、軸がブレてしまい、企業選びや面接で失敗する可能性が高まります。以下の問いを自問自答し、ノートに書き出してみましょう。
- 現在の不満は何か?: 残業時間、給与、人間関係、仕事内容、評価制度など、具体的な不満点を洗い出します。
- 次の会社に何を求めるか?: ワークライフバランス、高い年収、やりがいのあるプロジェクト、キャリアアップの機会など、優先順位を明確にします。
- 自分の強みは何か?: これまでの業務経験で培ったスキル(専門分野の知識、マネジメント能力、コミュニケーション能力など)、取得資格、人からよく褒められること。
- どんな仕事に携わりたいか?: 構造設計、都市計画、地質調査など、具体的にどのような分野でキャリアを積んでいきたいかを考えます。
この自己分析を徹底することで、あなたに本当に合った企業を見つけることができ、効率的な転職活動が可能になります。
書類はあなたの「顔」です。特に、これまでの実績を具体的に記載した職務経歴書は、あなたの強みや熱意をアピールする上で最も重要な書類となります。単なる業務内容の羅列ではなく、「何を課題と捉え、どのように行動し、どんな成果を出したか」をストーリー仕立てで書くことを意識しましょう。
自己分析と書類作成が完了したら、いよいよ応募です。興味を持った企業があれば、積極的に応募してみましょう。転職エージェントに登録すれば、あなたの希望条件に合った求人を厳選して紹介してもらえます。
面接は、あなたの熱意やスキルを直接アピールする場です。事前に応募企業の事業内容、企業理念、最近のニュースなどを調べておくことで、面接官に「入社意欲が高い」という印象を与えることができます。
数回の面接を経て、内定となります。
内定をもらった後、年収や入社日などの条件交渉が必要になることがあります。自分で行うのが難しい場合は、転職エージェントに代行してもらうのがベストです。エージェントは企業の年収テーブルや相場を把握しているため、あなたにとって最適な条件を引き出してくれる可能性が高まります。
新しい会社への入社日が決まったら、現職への退職手続きを進めます。円満退職を心がけ、後任者への引き継ぎを丁寧に行いましょう。最後までプロフェッショナルな態度を貫くことが、次のキャリアにも繋がります。
建設コンサルタント業界の転職ロードマップについては、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。
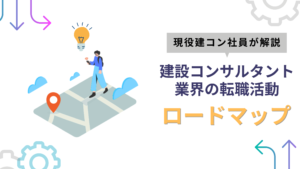
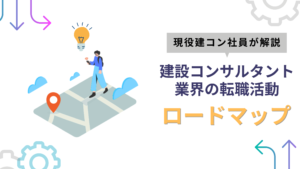
建設コンサルタントに転職する際の注意点
ホワイト企業に転職するためには、これまでの内容に加え、以下の注意点を押さえておくことが大切です。
専門分野を明確にする
建設コンサルタント業界は、道路、河川、橋梁、地質、都市計画など、専門分野が多岐にわたります。あなたの得意な分野や、今後挑戦したい分野を明確にすることで、より専門性を活かせる企業を見つけやすくなります。
資格取得の重要性
技術士やRCCMといった資格は、あなたの専門性を証明する上で非常に有効です。入社後のキャリアアップだけでなく、転職活動においても大きな武器となります。もし現在資格がなくても、入社後の取得支援制度が充実している企業を選ぶと良いでしょう。
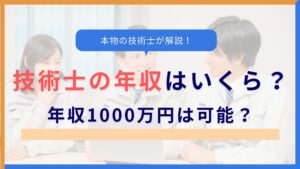
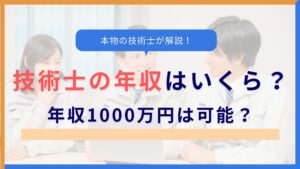
面接時の逆質問は「具体的な働き方」に踏み込む
面接官に「残業はどれくらいですか?」といった直球な質問をすると、身構えさせてしまう可能性があります。以下のように、より具体的な働き方をイメージできる質問をすることで、相手も答えやすくなります。
- 「御社では、繁忙期はどのような時期で、プロジェクトの平均的な残業時間はどのくらいになりますか?」
- 「有給休暇を取得する際の申請フローや、長期休暇の取得実績について、差し支えない範囲で教えていただけますか?」
- 「育児や介護など、ライフイベントと仕事の両立を支援する制度はありますか?また、実際に利用されている社員の方はどのくらいいらっしゃいますか?」
【総括】建設コンサルタントのホワイトランキング
建設コンサルタント業界は、激務と言われる側面もありますが、ホワイト企業は確実に存在します。重要なのは、口コミやランキングを鵜呑みにせず、本質的な見極めポイントを押さえ、自分自身の軸を持って転職活動を進めることです。
この記事で解説した「ホワイト企業の見極め方」や「転職ロードマップ」を参考に、ぜひあなたの理想のキャリアを実現させてください。
もし、転職活動に不安がある方は、転職エージェントの力を借りることも有効です。あなたの経験やスキル、希望条件に合った求人を紹介してもらえるだけでなく、企業には聞きにくい裏事情まで教えてもらうことができます。
あなたの転職活動が成功することを心から応援しています。
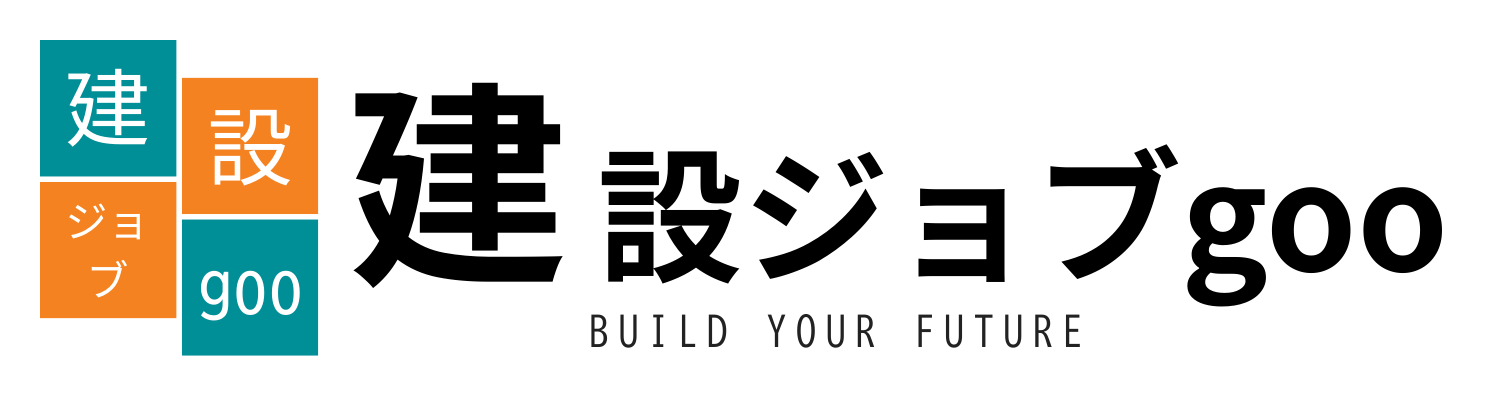


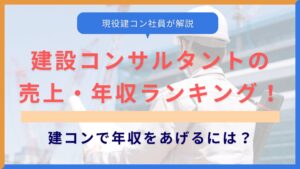
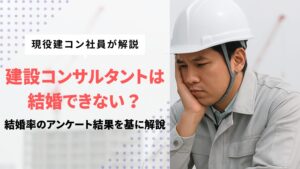
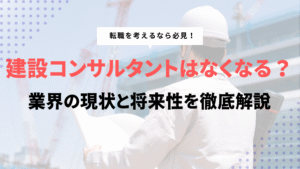
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] ワークライフバランスを重視する企業:昭和・平成初期の「仕事が第一」という価値観から、家庭などのプライベートを重要視する流れが主流になっています。ワークライフバランスの取れない企業は、優秀な人材が集まらず、結果として成長が停滞してしまう可能性があります。なお、建設コンサルタントのホワイト企業の見分け方やブラック企業の回避方法については、「建設コンサルタントのホワイトランキング|失敗しない【見分け方】」で解説しておりますので併せてご覧ください。 […]